デジタルが支える「顧客優先主義」
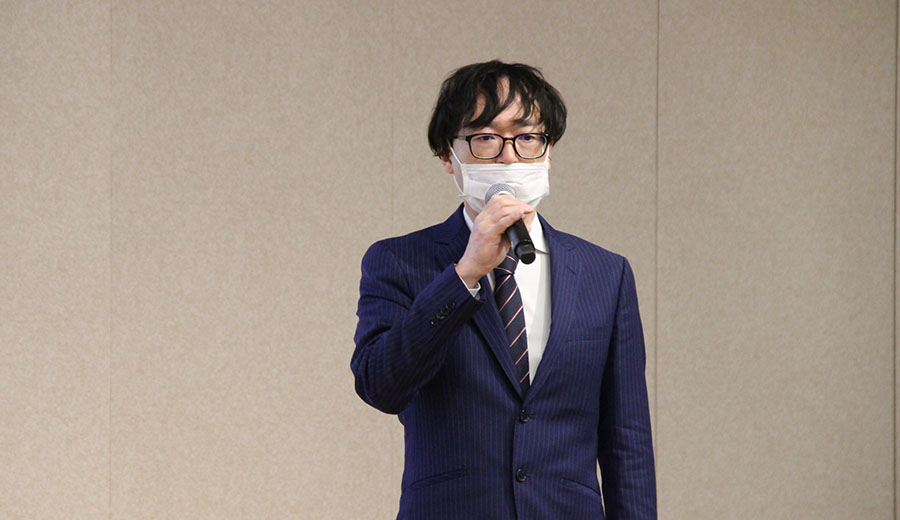
丸井グループでは、今後の経営にとって重要となるさまざまなテーマを考える場として「中期経営推進会議」をほぼ毎月開催しています。
2021年4月5日(月)、「デジタルが支える『顧客優先主義』」というテーマで、丸井グループとの取り組みを進めている(株)エーツー 代表取締役社長 杉山 綱重さんの講演と、アニメ担当役員である青木や当社からの出向社員とのトークセッションを行いました。
リユースホビーの販売を行う駿河屋を運営する、(株)エーツー 代表取締役社長 杉山 綱重さんにご登壇いただき、「デジタルが支える『顧客最優先主義』」というテーマでご講演いただきました。その後、当社執行役員 アニメ担当の青木、駿河屋へ出向している当社社員 吉田を交え、コロナ禍における店舗のオムニチャネル化などについてトークセッションを行いました。
エーツーさまと丸井グループ 共創の歩み(当社執行役員 青木より)
エーツーさまは、リユースホビーの通販売上が7年連続日本一の会社です。駿河屋のリアル店舗は88店舗あり、店舗売上は50億強となっていますが、そのうちの約3分の1が、マルイの3店舗によるものです。コロナ禍においても、デジタルとリアル店舗の相乗効果で、非常に飛躍している企業になります。
丸井グループとエーツーさまとの出会いは、5年ほど前に当社リーシング部から営業電話をかけたことがきっかけです。その後2018年4月に新宿マルイ アネックスの5階にワンフロアで駿河屋を展開していただき、取扱い高の拡大に大きく寄与していただきました。2019年12月には資本業務提携をし、2020年からは弊社からエーツーさまに社員が出向、さらに私がエーツーさまの社外取締役に就任いたしました。
新宿マルイ アネックスを皮切りに、マルイシティ横浜、博多マルイ、大宮マルイにご出店いただき、2020年7月にはマルイファミリー溝口の7階に買取りに特化した買取センターをオープン。こちらの一部は丸井グループ社員が運営を受託しています。今後も、買取センターを含めたショップ数の拡大をご提案中です。
丸井グループの物流会社であるムービングによる、マルイ店舗での駿河屋商品受け取りのほか、マルイウェブチャネル(丸井のEC)でも協業が進んでいて、今後も掲載商品の増加などで連携をさらに強化していきます。駿河屋さま全体のカードご利用のお客さまと、駿河屋さまでエポスカードをご利用いただいたお客さまの割合を見ると、性別・年代・地域などの構成が、真逆になっており、相乗効果・補完関係にあると考えています。
協業・投資関係にあっても徹底したビジネス視点と、強固な信頼関係が重要です。丸井のアニメ事業部を始めとして、丸井グループ全体でエーツーさまとWin-Winの良好な関係をさらに深めていきたいと考えています。

(株)エーツー 杉山さんによる講演
お客さまが望むことをとにかくかなえる「顧客優先主義」
株式会社エーツー 代表取締役の杉山 綱重と申します。さて、本日私がこうして会議に呼ばれているのは、おそらくエーツーが丸井グループ(以下 丸井)さんと対極の会社だからだと思います。丸井さんは非常に伝統がある会社で、上場企業ですし、収益性も高い会社ですが、エーツーは22年前に私がつくった会社ですから、丸井さんに比べればまだまだ本当にひよっこで規模も小さいです。そしてもう一つ違う点は、私が今48歳、会社を興したのが26歳の時で、言ってみれば、デジタルネイティブ世代の一番最初の年齢ということだと思います。
1995年は、インターネットの普及で世界が完全に変わった年でもあります。もちろんインターネットはそれ以前からあり、私ももともとパソコン通信が趣味でしたが、この普及によりパソコンのブラウザで、誰でもインターネットでつながれるようになりました。今の若い世代の方はまったく知らないと思いますが、それまではニフティサーブやPCVAN、アスキーネットなどのコンピューター同士を直接つなげるクローズドなネットワークというものが主流でした。
その当時私はとあるゲームショップで働いていて、勝手に通販サイトを立ち上げました(笑)。働いていた焼津市が昔の呼び方で「駿河」という地名だったので、屋号を「駿河屋」に決め、インターネット上で通信販売と通信買取を始めました。ちなみにこれが日本で最初のインターネット買取だったので、今、弊社がインターネット上のリサイクル通販シェアナンバーワンというのは、とても簡単な話なんです。
私の思う「顧客優先主義」というのは、「お客さまが望んでいるサービスを、どれだけ提供できるか」です。お客さまが望んでいることだったら、とにかくどんな方法でもいいから実現しましょう。それが当社の基本的な考え方です。
私が起業するにあたって最初に考えたことは、「顧客が『あったらいいな』と思うサービスを叶えること」です。当時は顧客がいなかったので、全部想像ですが(笑)。
例えば、自分の好きな本があるとします。でも昔は、著者やジャンル、出版社で検索することができなかったので、どこに本があるのかがわかりませんでした。また、出版社×著者などの情報で横断的に調べる方法もありませんでした。一つひとつ書店を訪ねれば調べてもらえますが、具体的にどこにあるかはわかりません。さらに、絶版になった本であれば古書店をたくさん巡らないと買えません。そこで、まず「最大レベルの品ぞろえをつくりたい」と考えました。
さらに、お客さんにとってそれをわかりやすく検索できるようにしたいと思いました。例えば、お客さまが価値が高いと思う本を売りたい時に、チェーンの買取サービス店に持って行くと買取ができなかったり、10円だったりする。でもそれが実はすごい価値がある本なのかもしれないですよね。こういうサービスではダメだと思い、インターネット上で事前に買取価格がわかるというサービスをつくりました。これが日本初なんです。
事前に買い取り価格を提示し、一定期間内に送っていただければ、状態にもよりますが、その値段で買い取ります。当社が通信買取で一番になれたのは、それを最初にやったからだと思います。お客さまが望むことを想定すること、それをすぐに実行してみて、お客さまの支持が得られなければ変えていくこと。この点は丸井さんとうちとの、もう一つの違いだと思います。
私がよく言うのは、「できたばっかりの会社で前例なんて関係ない。必要だったらすぐやる」です。その結果、現在月間PVは1億3000万、ユニークユーザー数は400万人ほどになりました。いろいろなモールで売っている通販サービスもありますが、うちは約93%が自社サイトの売上です。実は一時期停滞したこともありますが、新宿マルイ アネックスやマルイシティ横浜へ出店したあたりから、さらに売上が上昇しています。ここ10年間で、2億から14億へと、7倍もの成長をしています。

また、書店は近年ではなかなか売上規模を維持することが難しい業界ですが、日本でトップシェアの書籍卸し会社である日販さまとも業務提携し、日販さまの店舗を復活させるというプロジェクトも進めています。トライアルで、日販さまとの提携第1号店として、新刊書店の隣に駿河屋を出店しました。新刊書店でコミックなどが並んでいる横に駿河屋をつくり、壁はつくらずに、お客さまが自由に行き来できるようにする。駿河屋の中にはジャンルごとにコーナーがあり、新刊のコミックの下に中古の書籍があり、さらにその下にカンバッチなどのアニメ関連グッズを置いています。お客さんがほしいのは必ずしもコミックだけではなくて、一緒にグッズやフィギュア、CDを買うかもしれない。お客さまが買いに来ているのはあくまで自分が好きなコンテンツなので、お客さまの目線に立って陳列を行ったところ、非常にいい結果が出ています。お客さんが求めているのはコンテンツそのものなんです。だから取り扱いのないものをなくしたい。それをずっと続けています。
そういった流れでオムニチャンネル化も徹底的に進めています。マルイ店舗での受取り、店舗在庫の通販、店舗での通信買取などですね。GPS連動で近くの店舗にある在庫だけ表示する機能などを設けて、とにかくお客さまから見て便利にしています。
今後は、全国すべての大都市に駿河屋を出店します。というのも、通信買取も広がっていますが、店舗への持ち込み需要もまだまだかなり高いからです。駿河屋の店舗が増えることで、お客さまの利便性がさらに増していくはずです。さらに、東南アジアなど、海外でも駿河屋の展開をスタートします。最初にタイに店舗を出店し、続いて台湾でのサイトや店舗づくりを進めています。また、ほかの子会社でフィギュアの製造も始めています。駿河屋では、今後製造・販売したものを売りっぱなしにせずにリサイクルもするということを、あらゆるもので進めていこうと考えています。
アニメ事業担当 青木・出向者 吉田と杉山さんのトークセッション
「オンライン」と「オフライン」を切り分けない
青木:エーツーさまと常々話している中で、オンラインとオフラインの役割についての考え方に、非常に感銘を受けました。
杉山:なぜリアル店舗の出店を進めるのかとよく聞かれますが、私の中では、「リアルとインターネット」という切り分け方に違和感があります。今は皆がスマホを持っていて、いつでも、ほしいと思ったら数秒後には注文することができる。「だから店舗はいらない」というような考え方もできるかもしれませんが、むしろ私は全く逆で、店舗とネットがつながっていて、在庫がどこにあるのか事前にわかることも、できて当たり前だと思います。さらに、そのうえでお客さまにとって便利なのは何かということを考えることがとても重要です。
例えば、急に家に子どもが遊びに来ることになって、ゲームのコントローラーが足りず、明日どころか1時間以内にほしい。例えば、売りたいゲームソフトの買取価格を調べた時に、近くに店があったら持っていきたい。例えば、大量生産品だとものによって状態が違うから、現物をちゃんと確認したい。例えは、ふらっとお店に来て新しいものに出会いたい。こういうことが想像できますよね。
通信買取をインターネットで申し込んだときに、宅急便で送ればオンラインで、店に持ち込んだらオフラインと言われますが、それは違います。最初に申し込みをしたのがオンラインなら、店舗だってオンラインの一つ。店舗はむしろ、お客さまにおもしろさを提供したり、便利にするためのツールだと思っています。
吉田:「体験価値」という、丸井がリアル店舗に求める価値観と近いですね。

(左から)吉田、杉山氏、青木
青木:今は「OMO」という考えが重要視されていますが、今後、駿河屋が事業規模を拡大していく中で、オンラインとオフラインの拡大比率についてはどう考えていますか。
杉山:なかなか店舗の利用が進まなかったのですが、コロナ禍で一気に使用率が高まり、今までなかなか出店してくれなかった取引先さまも、出品が進んでちゃんと売れています。店舗からの通販もあるので、それを店舗の売上だと考えると、現在は通販が7割強ですが、いずれ通販6割、店舗4割くらいになると思います。
吉田:ありがとうございます。駿河屋さんのリアルとネットの融合を支えているのが、圧倒的なデータ管理の力だと思います。それによって同じ商品がリアルでもECでも変わらず買える、ということですね。
青木:5年前に当社のアニメ事業部の大きな初舞台となったコミックマーケット89で、私自身が売っていたトレーディングカードを、最近、駿河屋さまで買いました。駿河屋さんでは、すべての商品の、商品名と当時の販売価格、販売時期が管理されていて、当時4,630円のものを今は3,200円で売っているということがわかりました。このように、データがきちんと管理されているのはすばらしいと思います。販売価格が数十円のものにも手間をかけて利益を出せる秘訣や、データ管理の精度について教えていただけますか。
杉山:ネット通販は商品が登録されていないと販売できないので、すべて登録してあるのが当たり前ではありますが、登録にこだわるもう一つの大きな理由は、「お客さまがどんな理由でどんな商品がほしいのかはわからない」ということです。例えば、すごく高く売れるものを優先して登録して、そうでないものは手間がかかるので管理をしない、という企業もあると思います。ですが、それでは商品の価値を企業側が決めているということになりますよね。
吉田:なるほど。私が出向して一番最初に驚いた言葉は「この世にあるすべてのものをマスター登録する」でした。「そうしたらこの世のすべてのものを買い取って売れるでしょう」という考えに、深く納得しましたね。
青木:トレーディングカードやガチャガチャの商品、食玩の景品などを人力で登録しようと思うと、人件費や手間がかかると思いますが、どう解消されていますか?
杉山:基本的には、登録や商品製作のためにかけている人件費というのは、今のうちの会社の規模には本当は合っていないんだと思います。現在の年商が280億ほどですが、商品制作だけで年間の人件費が5億円、システム投資にも3億円くらいかけていますから、だいぶ高いですよね。こんなことをしなくてもこの売上を維持すれば、より高収益な企業になるということはわかっていますが、それだと商品の取り扱いが完璧になりません。私たちはそれよりも、いわば「インフラを提供する企業」をめざしています。例えば、通販の仕組みやPOSシステムを全部自社でつくっていますが、これは他社にも提供することができます。また、買取・再販売の価格は各社で違ってもいいですが、マスターデータをつくるのは1社だけで良い。先んじてつくることで、他社に提供でき、その収益で開発費を増やすことができます。そういう考え方でフランチャイズや、「supported by駿河屋」というネームと仕組みだけを提供する協力店舗をどんどん増やしています。
開発投資をやればやるほど市場が取れる理由は、一つは他社にデータを提供して収益を上げること。もう一つは開発投資を続けることで参入障壁ができ、市場のシェアを獲得できることです。
青木:なるほど。駿河屋さんのサイトのPVは非常に高いですが、お客さまだけでなく同業他社が、商品相場を調べるために利用しているのではないかと懸念があります。
杉山:当然そういったことはあります。他社の研修でも、「どうしても価格がわからなかったら駿河屋を見るように」と指示しているところがあると聞きました。うちの価格を見て相場を決めているなら、もはやプラスリーダーじゃないですか。すごく誇らしいですよね。京商という会社を買収した時に、執行役員の方と話をしていたら「自分は駿河屋さんを知りませんでしたが、息子に聞いたら知っていました」と。理由を聞いたらメルカリに出品する時に、駿河屋の価格を参考にするそうなんです。友人も使っているらしいですよと。全くお金は入らないですが、なかなか誇らしいですよね。その高校生もいずれ大人になって、どんどん駿河屋の認知が拡がれば、機会があれば駿河屋で買ってくれるかもしれないし、まとめて売る時は駿河屋を使ってくれれば良い。真面目な話、うちの相場は顧客がいるからこそ成り立つものなので、競合からいくら参考にされても関係ないです。
吉田:ありがとうございます。ちょうど今競合という話もありましたが、次はリアル店舗の価値についておうかがいします。駿河屋の中でも、マルイ内の店舗とほかの商業施設や路面店の違いはありますか。
杉山:マルイ内の店舗は、それ以外のお店とは顧客層が全く違っていて、新しいお客さまを取り込めたと感じます。地方の路面店は静岡でも北海道でも顧客層が似ていますが、都会の店舗に来るお客さまは新しい層だということがサイトPVにも明らかに表れています。例えば鬼滅の刃が気になっている、駿河屋を知らない都心のOLさんが、マルイに行ったらグッズが大量に並んでいて、思わず買ってしまう。それで駿河屋の名前を覚えてもらって、今度はインターネットで検索してサイトも覚えてもらえるというような、良い循環が起きていると思います。

とにかく品ぞろえを最大化する
吉田:Withコロナに向けて、杉山社長が考えていることは何かありますか?
杉山:先ほどもお話しした通り、「店舗のオムニチャネル化」つまり、店舗での通信販売や買取を2020年からかなり強化しています。郊外にあって大きな駐車場のある店舗は、新型コロナウイルスの影響でむしろ伸びていますね。実は業績が悪かった新刊書店でも、復活するどころか、むしろ通販を強化することで前年比140%になった店舗もあります。
一方で、都心型店舗は逆に店頭顧客が減り、なんとか通販で前年超えという感じなので、店舗においても徹底的にインターネット対応をして、スムーズに買取ができることが重要です。そのため、GPSと連動して近くにある在庫だけを表示する機能や、スマホで先に登録することで早く買取作業が終わるサービス「スマ得サービス」などで、店舗滞在時間をできるだけ短くしています。利便性も高めつつ、店舗における通販も強化する。これを今後継続していきます。
青木:最近、駿河屋さんのお店へ行くと買取コーナーに長い行列ができています。インターネット買取の仕組みもある中で、リアル店舗、それも新宿や横浜に来ていただけることはありがたいですね。新型コロナウイルスの影響がある中、あれだけ買取に並んでいただける想定されていましたでしょうか?
杉山:あまり気にしない人が多いのだと思います。実物も確認できますし、コロナ疲れもあってお店に来たいのかもしれないですね。
吉田:では続いての質問ですが、駿河屋が創業当時から貫いていることを教えていただけますか。
杉山:私は今も当社はスタートアップ企業だと思っていますが、一貫して「品ぞろえを最大化したい」という想いがあります。例えば、創業当時は「プレイステーション」が全盛の時代で、「スーパーファミコン」や「ファミコン」はもう古いゲームという風潮でした。大手チェーン店はその取扱いをどんどん縮小しましたが、私の考えは逆で、「その中にも価値が高いものがあるはずで、それが文化なんだ」と、ファミコンだけでなく、昔セガさんが出していた「SG1000」や、海外のメーカーのゲーム機のソフトなど、とにかくどんな古いものでも登録しました。ちなみに今は、Appleが「Macintosh」の前につくっていた「AppleⅡ」のソフトのマスターデータを整備して、高価買取リストをつくり、とにかく全部集めようとしています。

商売の鬼 杉山社長語録
吉田:ではここで、商売の鬼と呼ばれる杉山社長の語録を紹介します!まず「うちの会社に打ち出の小づちはないですよ」というのは、どういう考えですか?
杉山:当社は売上も利益も増えていますが、在庫が利益よりももっと増えています。利益が出ているからといって、キャッシュフローがマイナスではだめなので、在庫回転率を適切に管理する必要があると、商品担当や店長に言ってます。売上・利益を適切に伸ばしながら在庫が増加するような、健全な成長の中でキャッシュが一時的にマイナスになっているなら金融機関にも説明できますが、意味のない在庫増加は単にお金が減っているだけで、「単に利益が出ているから賞与を出せるかというとそうではない」という意味ですね。
吉田:続きまして「君の言っていることは数字や数式で表せるのかい」。
杉山:伝えたいことがさっぱりわからない時に、「あなたが言っていることは数字や数式で表せるんだよね?それができないような、雰囲気や感覚での意見はいらない」という意味でよく言いますね。
吉田:続いて「君は3歩の距離も全力で走っていますか?」。
杉山:これは創業のころに言った言葉で、今は言ってないんですけどね。当時はできたばかりで「人手が足りない」と言われたんですが、そもそも回転スピードが遅すぎると思って、個人IDを全員に設定しました。作業スピードをパソコンで自動計測できるようにして、それを個人に反映できる評価制度をつくったんです。その評価が良い人間は給与をどんどん上げていったら、全体の作業効率が本当に倍になったんです。だから、この言葉は「その人員は本当に必要なの?本気でやったらできるんじゃないか」という意味です。
吉田:ありがとうございます。商売の鬼、杉山さんの語録を胸に、これからも出向頑張ります!
青木:ありがとうございました!

- 登壇者プロフィール
- 杉山 綱重氏
(株)エーツー 代表取締役社長 - 1998年にリサイクル業界で初のインターネット通販事業「駿河屋」を開始。現在、全国に70店舗以上を展開する。


















