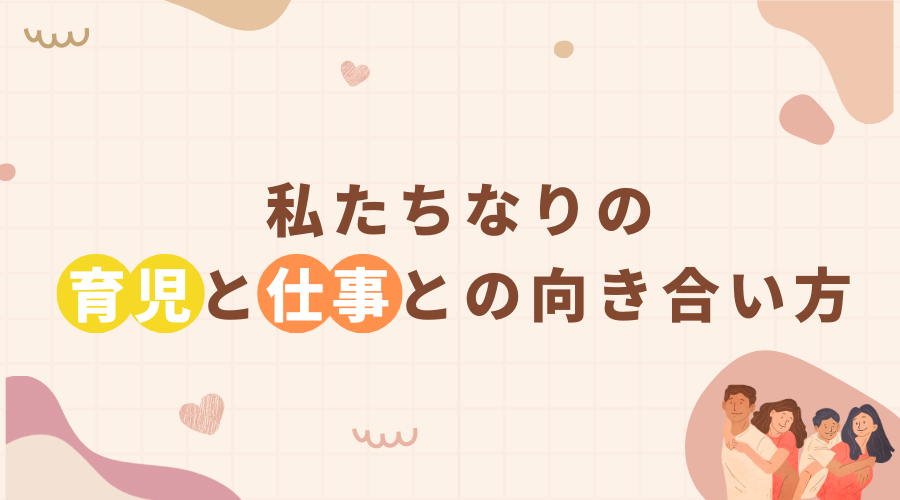ジェンダーバイアスにとらわれず「個」が輝くために

第5回はフリージャーナリストで日本政府主催の国際女性会議WAW!(World Assembly for Women)国内アドバイザーも務める治部 れんげさんに、寄稿形式でご登場いただきます。ご自身のお子さまとの会話や働くうえでの経験、そのほかまわりの方の声を踏まえながら、ジェンダーバイアス(性別役割分担意識)にとらわれず、「個」を尊重して輝くためのヒントを語っていただきます。
ある日のことです。近所の方と立ち話をしました。
「『主婦が家にいるのが当たり前』という仕組みだと、困っちゃうんですよね」
2児の母で、学校のPTA活動や地域の仕事など、いろいろなことを引き受けています。「本当は働きに出たいのだけれど難しい」と話してくれました。いつも笑顔で頼りになる奥さん、という雰囲気ですが、「主婦」として期待される役割を果たすのは、負担が大きいようです。私自身は子どもが2人いて、ずっと働き続けています。周囲には専業ママが多く、彼女たちの忙しさを目の当たりにしてきました。夫が仕事で忙しいため、家庭と地域のことは彼女たちが一手に引き受けているのです。
男性は外で働いてお金を稼いで家族を養い、女性は家事育児に専念して家庭を守るべき、という考え方を「固定的な性別役割分担意識」と言います。私のまわりには「女性」として「主婦」として、果たすべき社会的役割の重さに悩む人が少なくありません。
例えば「主婦は昼間、家にいるのが当たり前」という風に、社会が決める性別に基づく役割を「ジェンダー役割」と呼びます。ジェンダーに基づく無意識の偏見、つまりジェンダーバイアスは最近、多くの人の関心を集めるようになりました。なぜなら、日本では他の先進国と比べてこのジェンダーバイアスが強く、人の心を縛っているからです。それは人々が自分の好きなように生きることを邪魔し、生きづらさを感じる要因になっています。
女性だけではなく男性も、ジェンダーに基づく決めつけに生きづらさを感じることがあります。ある時、仕事の打ち合わせをしながらランチを取っていたら、私より15歳ほど若い男性からこんな相談を受けました。
「僕も夕方には仕事を切り上げて帰りたいんですが、それを言いにくい雰囲気があります」
この方は夜勤のある仕事に就いていました。部署内には働く母親がたくさんいて、その人たちに昼間勤務をアサインすると、男性や独身男女が夜勤に入ることが増えるそうです。私に相談をもちかけた男性は、もうすぐ初めての子どもが生まれるため、妻と一緒に準備をし、家事も分担したいという希望を持っていました。
しかし、職場で「僕も早番や昼間の勤務がいい」とは言いにくい、と言います。男性の自分が夜勤を嫌がると、子どもを持つ女性の同僚に夜勤をさせることになり、それはかわいそうなのでは、と心配していたのです。
相談をしてきた男性には「部署の責任者に伝えた方がいい」と話しました。子育てや介護など、家族のケアにかかわりたい、かかわる必要がある男性がその希望をかなえられないのはおかしいです。男性だから常に仕事を優先し、家族のことは妻に任せるべき、というのは、先に記した通り、是正すべきジェンダーバイアスです。
ジェンダーバイアスは大人だけでなく子どもにも影響を与えます。
2年前のことです。当時小学1年生だった娘に「学校について、何か意見はある?」と尋ねました。学校から業務改善に関するアンケートを受け取ったからです。すると、娘はこう言いました。
「名前の番号が、男の子は前、女の子は後ろなのが嫌。にいには6番で前の方なのに、私は26番で後ろの方なのはおかしい」
当時、娘が通っていた東京都内の公立小学校では、男女別の名簿が男子が先、女子が後になっていました。そのため、姓が同じでも、兄が6番、妹が26番と大きく違っていたのです。同じ都内でも前から男女混合名簿を使っている地域もありました。また、この話をしたら、関西在住の方に「え、まだ男子が先なんですか!」と驚かれたので、日本国内でも違いが大きいと思います。
娘の話を聞くまで、この事実に気づかなかった私は反省しました。3学年上の息子が学校に通っていた時は「男子が前」であることに違和感を覚えなかったのです。普段ジェンダーに関する仕事をしているのに、自分や家族が「優遇されているグループ」にいると、不公平感には気づきにくいのです。
ほぼ同じころ、娘のお友だちのお母さんから、こんなLINEを受け取りました。
「れんげさん、ジェンダーの仕事をしているんですね」
この人もまた、しっかりしたお母さんで、娘さんが2人います。話してみると「女子が名簿で後ろになるのはおかしいと思う」ということで、意見が合ってしばしば話をするようになりました。その後、子どもが通う学校では男女混合名簿が採用され、問題は解消されました。
ちなみに今の小学校では、性別に基づく差別を感じることは、基本的にはありません。男子も女子も「さん」づけで呼ばれ、先生は授業中に指名する際、できるだけ男女交互にするなど平等を意識していると思います。これは、40年近く前、私が小学生だった時とは大きく異なり、感心します。学校は性別に基づいて差別しようとは微塵も考えておらず、それでも無意識バイアスや慣習に基づく仕組みが残ってしまうのです。
「誰でもいつでも間違える可能性がある」という認識を持つことが大切
私は、仕事や家庭、地域や政治分野におけるジェンダー平等に関する仕事をしてきました。それでも、間違えることはある、という例をもう一つお伝えします。それは今から20年前のこと。私はビジネス雑誌の記者として、ITベンチャーを訪問しました。社長をインタビューするために会議室で待っていると、男性と女性が一人ずつ、部屋に入ってきました。
とっさに、男性を社長、女性を広報担当と認識した私は、男性に名刺を渡しました。すると、男性が「こちらを先に」と目で合図をしたのです。この企業の社長は女性で、男性は広報室長だったのです。「失礼しました!」と謝ると、社長は大丈夫ですよ、と笑顔で言ってくれたのですが、この時の失敗は今でも何度も思い出します。
当時私は、大企業の経営者に取材する機会がよくありました。取材相手はほぼ全員男性で、自分より年上、時折、親より年上の人もいました。場数を踏むうちに「若い女だからといってなめられてはいけない」と思うようになりました。なめられると、取材にも響くからです。ある時、とある会社の社長から「れんげちゃんには教えてあげようかな」とバカにされたことを機に、いくつか注意するようになりました。
第一に、スカートは履かずにパンツスーツを着ること。第二に、髪はひっつめて結ぶこと。第三に、笑顔を見せないこと。第四に、取材先の有価証券報告書や関連記事などを読み込み、重要な部分に付箋を貼った資料の束を持参すること。「これだけ予習してきた」ことを見せれば、なめられないと思ったのです。
こんな具合に性別と年齢に基づき、軽んじられる悔しさを痛感していたのに、自分が女性経営者に対してバイアスを持っていたとは、恥ずかしいことです。
皆さんも振り返ってみると「そういえば、無意識のバイアスがあったかもしれない」「男性と女性で扱いを変えていたかもしれない」と気づくことがあるかもしれません。気づくことは改善の第一歩だと思います。
ジェンダーバイアスに気づくために本を読んだり研修を受けたりすることは有効です。それに加えて「誰でもいつでも間違える可能性がある」という認識を持つことが大切です。「自分は間違えるかもしれない」と思っている人は、間違いに気づき、修正することができるからです。
特に、組織内で優位なポジションについている人は、部下や後輩からダメ出しを受ける機会がほぼないと言えます。その場合、家族や友人など、信頼できる相手からダメ出ししてもらうことが有効だと思います。私は、子どもとの会話で気づくことが多いです。
昨年の春、息子と娘と一緒にスターバックスに行った時のことです。私はコーヒー、娘は焼き菓子と紅茶、息子がいちご風味のドリンクを注文しました。ピンク色で春らしい息子の飲み物を見た私はつい「女子っぽいね」と言ってしまったところ「なんで、ピンクは女って決めつけるの!」と指摘され、「ごめん、ママが悪かった」と即座に謝りました。こんな風に、子どもとの会話は私にとって重要なバイアス是正装置です。

子どもたちが本物の花を見てつくった「紙の花」は、それぞれ違って多様性を表しているように感じます
自身のバイアスに気づき、是正することが次世代のチャンスを増やす
最後に、ジェンダーバイアスについて考える時、思い出すのは自分の会社員時代のことです。私は大学を卒業後、経済系出版社で16年間、記者として働きました。この会社の説明会では、ニューヨーク帰りの男性記者がイキイキと楽しそうに仕事について話していたのが印象に残りました。社長・役員面接の際、「私も、この人みたいに働きたい。こういうカッコいい記者になりたい」と話しました。この時、登壇していた記者は男性で、私自身は女性ですが、社長も役員も「君は女性だから無理」とは一言も言いませんでした。面接では、入社したらどんなことに取り組みたいか、大学で学んだことをどう生かしたいか、尋ねられました。
私が就職活動をした1996年、多くの大企業が女性は事務職、男性は営業といった具合に、性別に基づき職種を分けていました。そういう時代にジェンダーバイアスのない採用、育成をしてくれた勤務先には、今でも感謝しています。もし、初職の上司や先輩から「君は女の子だから」と軽い仕事を割り当てられていたら、今、私はこんな仕事をしていなかったでしょう。
性別や年齢などの属性ではなく、個人の意欲や能力を見ることは、組織内において人を活かすことにつながります。多くの人が自身のバイアスに気づき、是正することを願っています。それは次世代のチャンスを増やすと同時に、個が活かされる組織をつくることにつながるでしょう。
―前回ご登場いただいた山本さまより「日本の子育てで大事だと感じていることはありますか?また、子どもの幸福度の向上に必要なことは何だと思われますか?」というご質問をいただきましたが、そちらについていかがでしょうか。
個を尊重することだと思います。生まれてきた時は、元気でいてくれればいい、と多くの親が思いますが、段々と欲が出てきて、あれも、これもできるようになってほしいと考えてしまい、子どもにプレッシャーをかけるようになります。
「適切な期待」は子どもの自己肯定感につながり好ましい一方、親が果たせなかった夢を子どもに賭けるような「過剰な期待」は、子どもの人生を損なうと思います。子どもに対して、どうしても「この学校に入ってほしい」「この職業に就いてほしい」という気持ちが湧く場合、親自身が歩めなかった人生を、子どもの人生によって上書きしようとしている可能性があります。
学校でも仕事でも、子どもにそれを求めずにいられないなら、親自身がやってみたら良いと思います。親が自分の人生を思い切り生きていたら、子どもを過剰に縛ることもなくなるでしょうから。