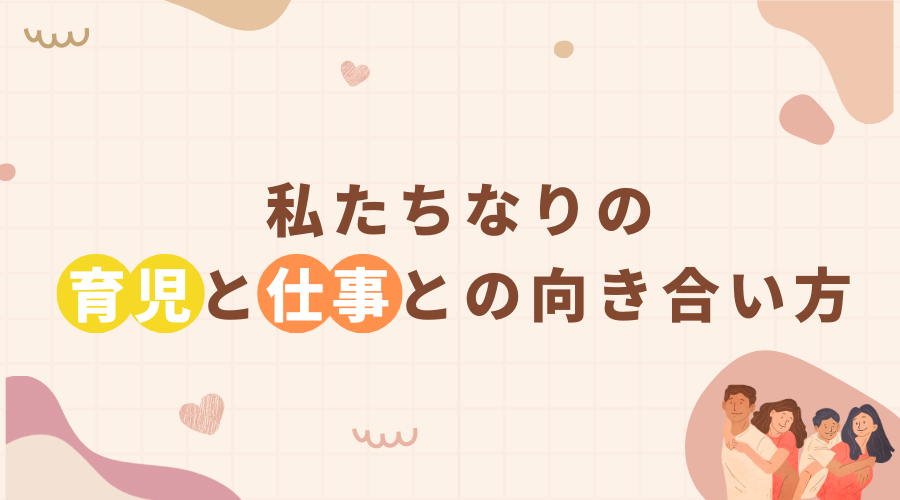弱点こそ魅力であり個性

すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現に向けて、各界のリーダーから提言をいただく連載コンテンツ「Inclusion Rally」。第9回目は「人の個性を大切にしたチームづくり」というテーマで、株式会社スティーブアスタリスク 代表取締役 CEOの太田 伸志氏に、個性や多様性に対しての想いや、これからの働き方についてうかがいました。
――幅広い分野において、アイデアとテクノロジーの力でクリエイティブコンサルティングを行うという現在のSteve* inc.(スティーブアスタリスク)という会社を立ち上げるきっかけになったご自身の経験や事業にかける想いについてお聞かせください。
僕たちの仕事は、長期戦略を含めた"クリエイティブコンサルティング"と、コンセプトメイキングからデザイン制作までを含む"制作"です。また、取材および原稿のライティング、フィクション・ノンフィクションを問わない作家活動、トークイベントなどの出演、作詞・作曲、イラストレーション、撮影なども行っています。つまり、アイデアが重要な仕事すべてです。
「Steve* inc.(スティーブアスタリスク)」という社名をつけたのは、僕がAppleの前CEO スティーブ・ジョブズに憧れていることが理由です。昔から、Appleの製品を買うことや、新製品発表会でのジョブズのプレゼンが楽しみで仕方がありませんでした。ですが、同時にデザインの仕事に対して疑問を持つこともありました。例えば、お菓子やジュースの中身よりも、パッケージの格好良さやCMに出ている芸能人の話題性の方が重要視される。そんな本来の商品の魅力よりも話題性や外見に注目する風潮に、疑問を感じていました。もちろん、対立構造だけではないと思いますが、10年ほど前は、「そんな違和感を持つこと自体変だ。デザインはそういうものだ」という空気が強かったような気がします。
ジョブズは、そんな誰もが本当は思っている違和感に正面から挑む人だったと感じています。例えばiPod。昔は音楽を聞く=10曲程度入っているCDを選ぶ。という行為だったものが、数千曲を持ち運べるようになった瞬間、人々は音楽をどう聞くのかということについて考えるようになりました。つまり、単なる最新音楽プレーヤーをつくったのではなく、音楽に対しての新しい概念をつくったのです。つまり、業界の構造自体をデザインの力で変え、世界に「このほうが良くない?」という問いかけを発信していたのではないでしょうか。真面目に話すのは照れますが、もしジョブズが生きていたらどう思うだろう...と考えて、いつも仕事をしています。

年に1度、みんなで集合写真を撮影します。徐々に増えてきました。

格好つけていないときは、こんな雰囲気です。
例えば、studio CLIP(スタディオクリップ)のサステナブル活動「FUNSUS(ファンサス)」には、再生紙を利用したショッパーや落ち綿を使った洋服の開発などが含まれますが、活動の指針となるネーミングや考え方から考えさせていただきました。studio CLIPは、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案している、30~40歳代の女性をターゲットにしたブランドです。そのため、世界規模での社会問題意識ではなく、もっと小さな、もっと身近な、生活に紐づけることで自分ごと化していただきたいと考えました。
昨今、あらゆる企業がサステナブル活動を意識していますが、「やらなければならない」という、危機感ともいえるストイックなものが多く溢れている気がしています。studio CLIPは、「世界を救うために何ができるのか」という大義というよりは、日々の生活の中で小さな喜びを見つけたいというお客さまが多いブランドのため、自分の中のちょっとした気持ちから参加できる想いのようなものをサステナブル活動の中心に据えられないかと考えました。そこでつくったコピーが、「明日も、たのしいといいな。」です。「地球を救いたい」というような大きな願いではなく、「今日もおいしいご飯をつくってしあわせに過ごしたい」という想い持ち続けることも大事なサステナブルな活動だと思うからです。その気づきを込めながら、アウトプットであるロゴや映像、Webやショッパーなどのクリエイティブディレクションを行いました。映像は、いわゆる告知動画ではなく、毎日その想いを大切にしたいという願いを込めて「子守唄」をつくりました。作詞を担当しているので、ぜひ聴いてください!

再生紙で制作したショッパーは、さまざまな動物の想いを表現したデザインに
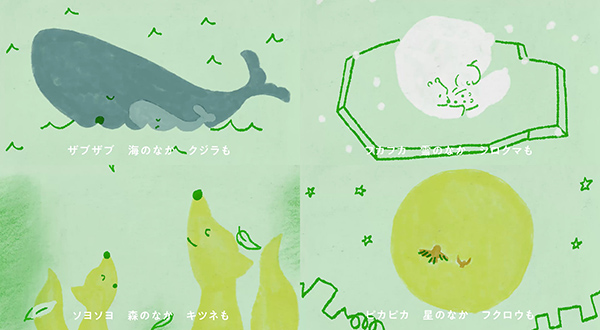
「明日も、たのしいといいな。」というメッセージを込めた子守唄もつくりました
studio CLIP FUNSUSサイトはこちら
https://www.dot-st.com/cp/studioclip/funsus/
自分の何かが0でも、集まればきれいな六角形になる
――数多くの仕事をされてきた中で、なぜ「個性」や「チーム」が大切だと気づいたのか。「弱点こそ魅力であり個性」という考えを持つきっかけを教えてください。
あらためて考えると、きっかけは2011年の東日本大震災だったと思います。宮城県にある実家と連絡が取れなくなり、2週間後に何とか高速バスで現地へ向かいました。恐怖をあおるような津波の映像がくり返しテレビで流れるだけで、情報も限られている中、高速道路のサービスエリアでの休憩中に、居合わせた方と仕事の話になりました。消防士や警察の方たちは「プロフェッショナルとして多くの人を助けなければ」という目的で現地に向かっている中で、僕はデザイナーですと名乗るのが恥ずかしいと感じました。しかし、その気持ちを素直に伝えたところ、「デザインを通じて情報を多くの人に伝えてほしい」と言われ、伝えるべき想いを伝えるという役割を担いたいと思うようになりました。
人間は、ついつい自分を大きく見せようとしてしまいます。ですが、勇気を出して弱みをさらけ出してみると、思いもよらない視点の優しい言葉が返ってくることもあり、自分がやるべきこと、やれることについての気づきを得られると感じています。会社のメンバーにも、完璧な人は一人もいません。僕も電車の乗り過ごしが異常に多かったり、スケジュール管理が恐ろしく苦手だったり、できないことがたくさんありますが、それらを一つずつ克服しようとすると時間がかかります。ですが、ありがたいことに優秀なメンバーたちがそんな僕の弱点をサポートしてくれるので、逆に自分の得意なことでサポートできるようにならなければと感じています。でも、そのほうが自然だし、自分に何ができるのかと向きあう時間が増えるほうが、人生にとって大切なのではないでしょうか。
個々の各能力を100点満点の六角形で表した時に、すべてで50点を取るよりも、どこかが10点でも良いから、得意なところを100点に伸ばしていく。そうすると、一人では不完全でも、集まることで完璧な六角形になりますよね。企業として強くなるためにも、弱みをさらけだせる環境が大事だと感じています。

――弱点を受け入れ、魅力を活かすのは簡単ではないと思うのですが、どのような意識を持って向き合えば良いでしょうか。
僕は、お酒を飲みながら人とゆっくり話すことも好きです。会話って、一方的なプレゼンと違って、相手に合わせて話しますよね。僕が弱点を出せば、相手も言ってくれることも増えます。さらけだすことの得手不得手よりも、さらけだしてもらったことにどう応えるかが大切です。「好きなことを言い合う=喧嘩をした方が良い」という意見もありますが、ぶつかり合うということは、お互いが言いたいことを一方的に言う会話のことで、本質ではないように感じます。僕は、言葉として表に出るもの以上に、もっと相手の本音に近づきたい。だから自分も本音で話さなければならないと思っています。
とはいえ、そうやって辿り着いた本質が優しいことだけとは限りません。僕は学生時代、サッカー部に所属していたのです、サッカーはレベルの差が明確です。夢があるのは良いですが、県大会にも出られないのに、ワールドカップ優勝が夢だというのは厳しいですよね。もし、本当にワールドカップで優勝したいのならば、夢の実現までを逆算する必要があります。今何をすれば良いかを考えた時に、今の10倍は練習しないとだめだと気づくかもしれない。それをストイックに実行するのも良いし、これは無理だと思ってサッカーのコーチをめざそうと夢を変えても良い。自分の弱いところを認めることで、宝くじのような運任せではなく、リアルな夢に向かって進むスタート地点に立てるのだと思います。
100%同じ人なんて存在しない。自分を普通だって思ってほしくない
――「自分らしさ」を大切にしたい一方で、自分に自信がない人も多くいます。自分をさらに愛せるようになるためのアドバイスはありますか。
今はすごく複雑な時代で、「悩みの種類」も、より繊細になってきていると感じています。僕は大学の講師もしていますが、20年前の僕と今の学生では悩みの次元が違います。例えば「自分らしさは、どうやって見つければ良いのでしょうか」。そんな悩みを打ち明けてくれる学生も多いです。
文豪の太宰治は、裕福な生まれで頭も良く、容姿にも恵まれていたにもかかわらず、毎日悩んでばかりいたと言われています。今の学生の悩みもそれに近い太宰型なのではないでしょうか。周りの大人たちからは、自分が学生のころに比べれば贅沢だと一蹴されそうな悩みですが、僕は、理解しようとしない大人が悪いのではないかと思っています。つまり、想像力です。「自分自身が考えもしなかった課題を、学生が提供してくれている」という感覚になれれば、20年前には気づかなかった思考に想いを馳せられる。太宰も、もしかしたらまわりの大人に相談しても自分の悩みを理解してもらえないと思っていたのではないでしょうか。悩みの種類だけを聞いて、瞬間的に「深い悩み」「浅い悩み」という判断はできません。だからこそ対話が必要ですし、想像力が必要です。
自分に自信がない人へ、自分をさらに愛せるようになるためのアドバイスというのはおこがましいですが、どんな人も唯一無二の個性があると思います。どこで生まれ、どこで暮らし、何を食べて、部活で何をし、どんな本を読んで生きてきたのか。100%一致する人生なんてないはず。今の人格形成につながる掛け算は、人生の積み重ねにあります。つまり、自分の人生としっかり対話すれば「自分らしさ」は必ず見つかると思います。「普通の人」、そんな人はいないし、そうやって見つけた自分だけの今の個性を愛する努力も必要なのではないでしょうか。

多くの大学や企業で「クリエイティブディレクション」の講義も行っています
めざすはあらゆる分野にクリエイティブディレクションを
――「魅力的な個性」を持つ仲間と、今後どのようなことを実現したいですか。
世の中では広告=クリエイティブと思われていることもまだまだ多いですが、僕はすべての業界にクリエイティブディレクションを浸透させるべきだと思っています。クリエイティブの概念が入っていない領域にも、見た目の美しさだけでなく、仕組みや構造の部分でジョブズのような「このほうが良くない?」という問いかけをし続けていきたいです。
例えば、「学校」なら、パソコンを持ち込んでインターネットに常時接続しながら学生がテストを受けても良いかもしれない。だって、実社会も仕事で何か解決しなければならない課題があれば、あらゆる情報網を駆使しながら、それを頭の中で繋げて答えを出さなければならないことばかりです。AIの時代に記憶力重視の能力評価は違和感を感じます。「街づくり」であれば、どんな商業施設や住宅街をどこにつくるのかだけではなく、例えば住居を東京やロンドンに持っていても、東北の小さな街のために働きたい。という人を増やす環境づくりも可能な時代だと思います。人口が1万人の街なのに労働人口は1000万人だとしたら、夢がありませんか?単純に地理的なエリア内での人口が増減という概念にも、違和感があります。
店舗名のネーミングやロゴ、コピーを含む店内装飾を担当した、三重県伊勢志摩にあるコインランドリー「MYMY LAUNDRY(マイマイランドリー)」のブランディングでは、国際コインランドリーEXPOの「コインランドリー店アワード2021」で最優秀賞をいただくことができました。クリエイティブでどこまで表現できるかへの挑戦でしたが、コインランドリー界でも認められたということがうれしかったです。これからも、業界や従来の常識に縛られず、さまざまな事業領域にクリエイティブディレクションを入れるために挑戦していきたいです。

国際コインランドリーEXPOの「コインランドリー店アワード2021」で最優秀賞を受賞
撮影:畑 拓
――前回の加来 幸樹さんよりいただいたご質問です。「取引先、社員、そして家族、さまざまなステークホルダーとのパートナーシップがますます重要になる時代だと思いますが、太田さんが考える『良いパートナーシップを発揮するために大切なこと』は何ですか?」
「助けてもらう」ことではないでしょうか。もし人を助けて感謝されたら、また何かしてあげたいと思いますよね。一方的に頼るという意味ではなく、助けてもらい、自分もいつか助けてあげたいと思う。結局、人生は助け合いなので。
僕は基本的に性善説で生きていますが、過去を振り返っても、その方がうまくいっている気がします。他人を信じず壁をつくったままでは、たとえマイナスが1で済んでも、プラスも1しか生まれません。逆に、相手を信じてみれば、たとえマイナスが20くらいあったとしても、プラスも30くらいあると感じています。相手に壁を無理やり壊してもらうことはできませんが、壁を壊す選択肢もあるかもって伝えたいです。
キャリアとしても、僕は最初からデザインの道を選んでいたわけではありません。20年前の東北では、まわりにデザインで食べている人なんていなかったですし、それが仕事になるなんて考えたこともありませんでした。プログラムが得意だったこともあり、大学卒業時、映画『マトリックス』の主人公 ネオに憧れてシステムエンジニアになることができました。仕事はとても苦しかったですが(忙しいという意味ではなく、好きではないことを頭に詰め込む作業が)、その給料で大好きなデザイン書や、Appleの製品を買うことが喜びでした。つまり、当時の僕が考える僕の人生は「我慢してもらった給料で、好きなものを買う」ことだと思っていたんです。
そうやって、仕事と趣味は違うと頭のどこかで割り切って、クールぶって生活していましたが、2001年のニューヨーク同時多発テロの信じられないニュースを観た時に、人生何が起きるかわからないのであれば、本気で好きなことに挑戦するべきだと感じました。その時から僕の人生は「好きなことを、もっと好きになるために働くべき」と考えるようになりました。プログラムとデザインが合わさったWebデザインという領域がちょうど2000年代に世の中で普及したり、『マトリックス』を配給しているワーナー・ブラザースでのWebデザイナーの募集にも受かったりと、運も味方をしてくれるようになった気がします。
壁をつくって生きていても、人生を約束されているわけじゃない。それならば、壁を壊して正直でいれば、きっと皆で助け合って生きていけると信じています。

-
Profile
太田 伸志氏 1977年宮城県生まれ。東北学院大学経済学部卒。
映画『マトリックス』の主人公ネオに憧れてシステムエンジニアとなる。その後、約15年にわたりクリエイティブディレクターとして、サッポロビール、SONY、資生堂、Honda、Canonをはじめ、数々の企業ブランディングに携わる。また、武蔵野美術大学、専修大学、東北学院大学の講師も歴任するなど大学や研究機関との連携や、仙台市の公民連携検討会の委員を務めるなど幅広く活動。作家、唎酒師でもある。Sony Music『大福くん』アニメ脚本執筆。Pen Online『日本酒男子のルール』連載。七十七銀行FLAG『大学で教えてくれないことは東北の居酒屋が答えをくれる』連載。文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品、グッドデザイン賞、ACC賞をはじめ、受賞経験多数。
 ―次回ゲストへつなぐラリー
―次回ゲストへつなぐラリー
- 「私らしさ」とはいったい何か。そんなものが自分にあるのかと悩む若者が増えている気がします。僕は髙木さんに初めてお会いした時から、唯一無二の「髙木さんらしさ」を感じているのですが、ご自身で自覚している「私らしさ」は何だと思われますか?また、「私らしさ」に悩む若者へ伝えてあげたいことはありますか?
- Steve* inc.
- 太田さんが代表を務めるクリエイティブカンパニー 株式会社スティーブアスタリスク
- https://steveinc.jp/