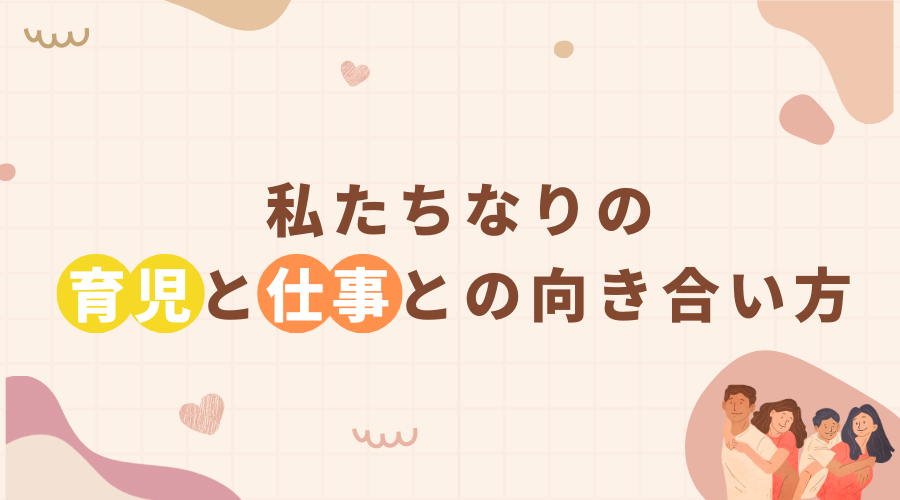誰もが尊重され、多様な人が共存できる社会をめざして
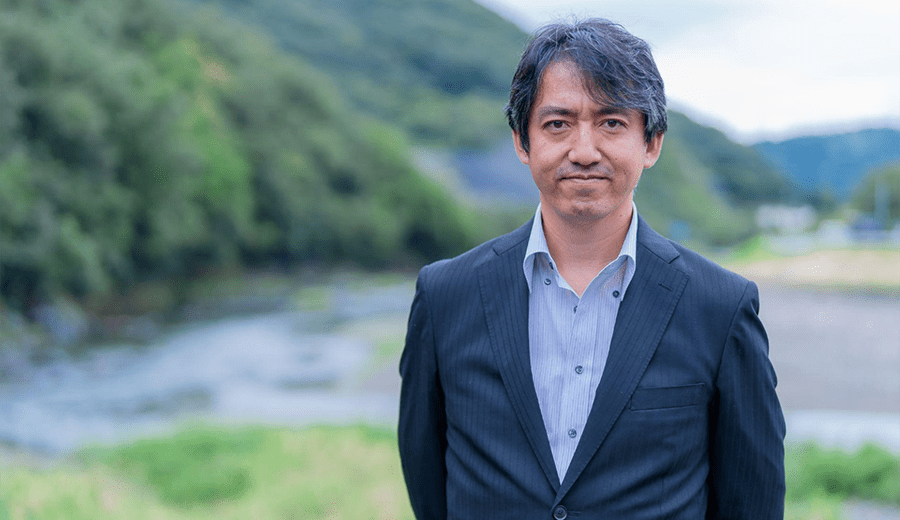
すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現に向けて、各界のリーダーから提言をいただく連載コンテンツ「Inclusion Rally」。
第11回ゲストとして、全国44都道府県で重度訪問介護などの事業を展開し、介護業界を取り巻く課題の解決に取り組む高浜 敏之氏にご登場いただきます。
介護難民問題を解決するために第一線でソーシャルインクルージョンを進めている高浜さんに、「高浜さんの考えるソーシャルインクルージョンとは何か」「多様性の本質とは何か」について、ご自身の経験を踏まえながら語っていただきます。
心理学に近い介護の現場に興味を持ち、自分の中の差別に気づいた
――2020年8月に、株式会社土屋という重度訪問介護にかかわる会社を立ち上げた高浜さん。どのような経緯で会社を立ち上げたのか、またどのような事業を行っているのか、教えていただきたいです。
メインの事業は、重度障がいのある利用者への訪問介護を24時間365日行う「ホームケア土屋」です。加えて、介護人材の養成を目的とした「土屋ケアカレッジ」など、人材育成と活用、その両輪を土台として重度障がい者のケアや介護業界の課題に立ち向かっています。
現在は介護の世界で会社を立ち上げていますが、私自身や家族が障がい者でもなければ、身の回りでそういった方との接点が多かったわけでもなく、介護の世界とは無縁でした。
私は学生のころから、自分の心や人の心に関心が強く、哲学や心理学に傾倒していました。ちょうどそのころ9.11同時多発テロやイラク戦争が勃発し、時代の空気感も相まって、自身の今後を考えるようになりました。
悩める若人であった私は、同じ価値観を共有できる仲間と夜な夜な世の中の批評をしては、「自分はどう生きるか?」を語り合っていました。その中で、すでに介護業界に携わっていた仲間の話を耳にし、自分の一つの憧れであった心理分析やカウンセリングと、介護などの"ケア"の現場が似ているのではないかと考えたのが、介護に関心を抱いたきっかけでした。
その後、ヘルパー2級の勉強に取り組んでいた私は、自身も障がい当事者で現在参議院議員を務める木村 英子さんが代表を務める障がい者自立支援団体でのアルバイト募集を目にし、迷わず応募しました。
当時、その団体が行っていたのは、現在の重度訪問介護の前身となる介護事業で、実務経験を積む中で、私は、介護という事業に確かな手ごたえを掴みました。介護する側と介護を必要とする側が一対一になって向き合い、そこに何らかの介助が発生することが、確かに自分が相手の役に立っているというやりがいを感じさせてくれたのです。
ただ、時には障がいを持つ相手との価値観の違いやそれによる葛藤、いさかいが生まれることもありましたし、そこでの毎日はこれまでの自分の価値観を塗り替えていくような作業の連続でもありました。
当時学んだ大きなことの一つが、自分の心の中にあった無意識の差別に気がついたことでした。介護の現場はストレスフルで、場合によっては障がい者の方から理不尽とも思えるような言葉を投げられることもあります。そんな時、私は「受容する」という意識で受け流していたのですが、そのことを木村さんに見抜かれ、「理不尽なことを言われたとき、健常者が相手だったら反論するところを、障がい者だからと飲み込んでしまうのは差別だ」と叱られました。当初は納得がいかなかったのですが、自分が本当の意味で障がい者の方と向き合っていなかったことに気づかされました。
受け流すのではなく、時にはケンカもしながら対話をしていく。そんな介護現場でのコミュニケーションのあり方にますます魅入られ、介護の道を進んできました。
多様であることは、価値観を緩めて楽になること
――株式会社土屋のビジョン・バリューに込められた想いを教えてください。
私たちの会社は、障がいの有無に関係なく「個の自律性が保障され、自由と規範が、多様性と全体性が共存する、オープンでありながら安全な交響圏」の実現をめざし、「多様な声が聞こえる交響圏へ」をビジョンとしています。
私は介護業界でのキャリアを歩む中で、障がい当事者として声を上げ、社会のあり方を変えてきたカリスマたちに出会ってきました。先述の木村さんに加え、日本の障がい福祉のパイオニアで重度の脳性まひ者でもある新田 勲さんもその一人です。木村さんや新田さんといった、いわば革命家ともいえる障がい当事者の存在を知り、その人生に触れたことで、彼ら彼女らのエネルギーの大きさには大変な感銘、そして尊敬を抱いています。
ハンディキャップを持ちながらどれほどの強い意思をもって苦難を乗り越えてきたか、その苦労は計り知れません。「こんなにすごい人たちを排除する社会であってはならない」という純粋な想いは、障がいがあろうとなかろうと、個人が等しく互いに尊重される世の中をめざすべきだと私を奮い立たせました。
当事者運動に参加する一方で、ボランティアや社会貢献団体が主催する多くのホームレス支援や難民支援運動にも参加してきました。
当事者でない人達にとって活動の源泉となるのは、"困難を抱えている他者に手を差し伸べて、多様性のある社会をめざそう"という理念にほかなりません。他者の痛みに共感を抱き、誰一人取り残さないより良い社会にしようという利他愛に自分自身も感銘を受け、共感や理解を通して緩やかに同じ社会の中で多様な人が共存できる、そんな社会の実現をめざしたいと考えたことが、会社のビジョンにもつながっています。
――多様な社会を実現するには何が大切だと思いますか?
当初、健常者である私にとって障がいのある方は未知の存在でした。初めてかかわりを持った時、どう接していいかわからず、困惑や狼狽といったネガティブな感覚があったのも事実です。
やはり人は、障がいの有無だけでなく、価値観や文化・背景、人種やセクシャリティなど、自分自身や持ち合わせている常識と異なることに少なからず違和感や抵抗感を抱いてしまう生き物なのだと思います。多様であることはすばらしいことではありますが、決して簡単なことではなく、程度は違えど最初の心理的なハードルを乗り越えるまでは葛藤がつきものなのだと、自己の経験を踏まえて感じます。
しかし、その葛藤を乗り越えるプロセスは、自分自身の価値観を緩めていくことそのもの。視野をこれまで以上に広げるチャンスでもあるのです。
「気づかないうちに、狭い価値観になっていなかったか」「"常識"ばかりに囚われて、自縄自縛になっていなかったか」と、緩めた価値観であらためて世界を見ると、きっとそれまで以上に楽に生きられる自分に気がつくのではないでしょうか。
そして何よりまず自分が楽になることで、他者を許容できるようになり、多様性社会に近づくことができると信じています。

困った人が、いつ・どこからでも、助けにアクセスできる社会にしたい
――現在の事業を通してどのような社会・未来を実現したいですか?
介護福祉の世界において、私が課題に感じているのが、精神病院や障がい者施設のような閉鎖空間です。そもそもは、障がいのある人の面倒を家族で見る家庭内ケアが近年の核家族化で破綻し、悲しい事件も相次いだ結果、必要に迫られて国がこういった施設をつくったという経緯があります。そういった意味でもちろん、一定の大切な役割を果たしてきたことは理解しています。
ただ、こうした施設ではヘルパー1人で複数名の利用者を担当するため、一人ひとりに寄り添ったケアをすることは困難で、「当事者が自分らしく生きられるのか」という問題は解決できません。
私たちの手掛ける「重度訪問介護」は、重い障がいのある人が自宅で暮らすために必要な支援を受けられるためにつくられた公的サービスです。ヘルパーが自宅まで赴き、食事や入浴、排せつといった身体介助、家事や外出支援、必要な場合は喀痰吸引などの医療的ケアなど、24時間体制でのサポートを行うことで、障がいを持つ当事者の方が自宅で自分らしく暮らすことを手助けしています。
ただ、弊社もまだまだ人手不足で、全体の依頼の1/3程度にしか応えられていません。私たちがめざすのは、困っている人が助けを求めた時、その助けにスムーズにアクセスできる社会です。そのために重度訪問介護のサービスをはじめとする地域資源を日本中に根づかせていきたい。そして、その先では精神病院や障がい者施設といった施設が不要になる世の中をめざしていきたいと思っています。
そのためには、介護業界全体の課題である待遇改善にも取り組む必要があると思っています。ケアやサポートの現場は、利他の精神がベースにあるがゆえに、"やりがい搾取"になりやすい一面があります。ただ、私たちがめざす未来の実現には、多くの優秀な介護人材が必要です。そのためにも「介護職は薄給」という固定概念を変えるべく、給与水準の底上げや、介護職の地位向上にも努めています。
多くの人材がモチベーションをもって介護の業界、そして重度訪問介護のサポーターをめざす、そんな社会を実現したいと思っています。
――前回のゲストである髙木さんから質問をいただいています。
「昨今のオンラインコミュニケーションの発展にともない、人と人の『つながり』方が多様化しました。ハードルが下がった一方、目の前にいない相手に自分の想いや熱を伝えることの難しさに直面することも増えているのではないでしょうか。私は、常に自分のオリジナルな想いを表現し、真正面から伝えることを大切にしています。高浜さんが日々のコミュニケーションにおいて大切にしていることは何ですか?」
私がコミュニケーションで大切にしたいと思っていることは、ありきたりではありますが、時に「ただ聞く」ということです。私は以前、自分のアルコール依存症の回復のために数年間、セルフヘルプグループ*に参加していました。
その場所で話し手には「私を主語にして語る」ことだけが期待され、聞き手には「ただ聞く」ことだけが求められました。意見も提案もすることなく、瞑想者が自分の呼吸に気づき続けるように、「他者の声」に気づき続けることが求められました。その場所で初めて会った、課題を共有する人同士が交わすコミュニケーションを通じて、同僚や友人との日常のコミュニケーションよりもさらに深い、「響きあい」を経験することができました。
普段のコミュニケーションでは、このような姿勢は忘れがちですが、時折この経験を思い出すことを通じて、職場でのコミュニケーションが、オンライン・オフラインを問わず、多少なりとも円滑になるような気がします。弊社のバックオフィスや管理職の方々は、オンラインでの仕事が90%以上を占めますが、オフラインでも薄い交流しかできないこともあるし、オンラインでも濃い交流ができることもあり、姿勢次第だと感じています。
経営者として頻繁に発信を行う毎日ですが、たまには大好きな音楽に耳を傾けるように、意見や提案や反論をすることなく、人の話を「ただ聞く」時間を持てるよう努めたいと考えています。
*セルフヘルプグループ:疾病や障害、依存症、精神障害、犯罪被害や遺族など、同じ状況にある人々が相互に援助しあうために組織・運営する、自立性と継続性を有するグループのこと。自助グループとも呼ばれる。

-
Profile
高浜 敏之氏 株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動、認知症対応型グループホームの介護職員を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、新規エリア開発などを経験。
2020年8月、株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。
「探し求める 小さな声を ありったけの誇らしさと共に」を企業ミッションに掲げ、介護難民問題の解決、ならびに障害や難病がある人も、病院や施設ではなく地域で生きる共生社会の実現をめざす。