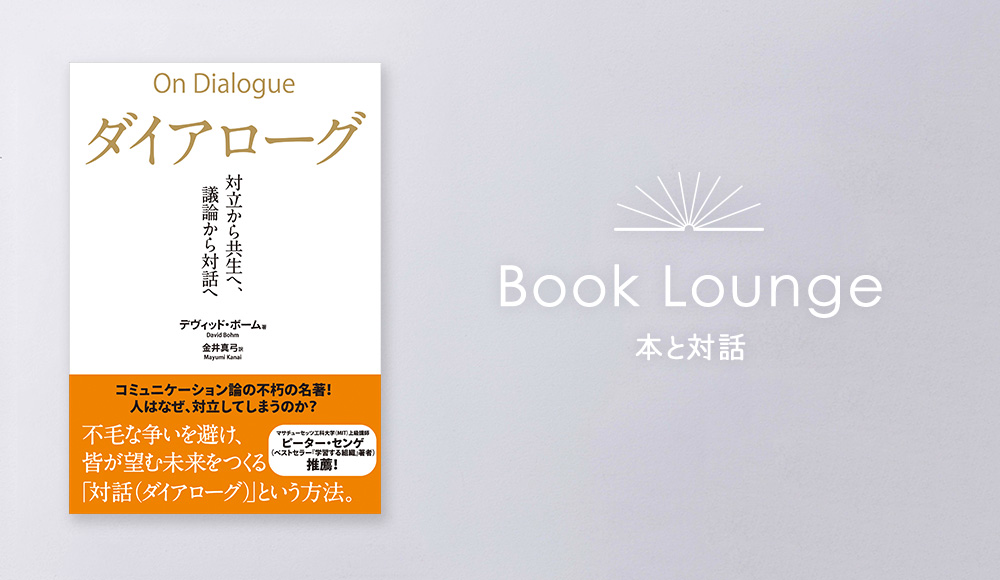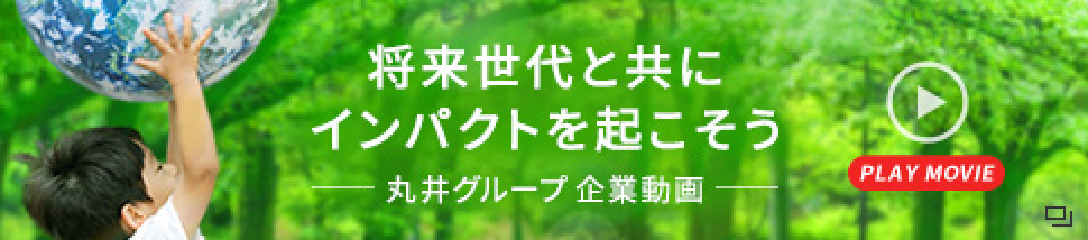#006-2 現代経済学の直観的方法

長沼 伸一郎(著)

これまでの資本主義の常識を変える「未来の経済学」
先月に続いて、長沼 伸一郎氏の『現代経済学の直観的方法』を取り上げます。
(あまりにおもしろすぎて、その魅力を語るのに一回では紙数が足りなかったためです。)
前回は、本書の第1章を通じて長沼氏の「直感的方法」について探りました。
そのねらいは「直感的方法」を理解し、使えるようにすることでした。
今回は、いよいよ本書のハイライトである第9章をたどりながら「直観的方法」のさらに奥へと踏み込みます。
今回取り上げるのは「メタファー」と「アナロジー」です。
本書で動員される比喩の多種多様さには目を見張るものがありますが、中でもメタファーとアナロジーは直観的方法の奥義と言っても良いほどパワフルな方法です。
そこで、この方法を使えるようになることを意識しながら、第9章を紐解いてみます。
本書のテーマは「暴走する資本主義をどうやって遅くするか」
でした。第9章ではその答えが示されます。
それは、これまでの資本主義の進歩に関する常識を大きく変えるもので、「未来の経済学」の試みでもあります。
ところで、資本主義の暴走はすでに19世紀から始まっていました。
しかし、その暴走の仕方にはこの数十年間で質的な変化が起こっているのです。
その変化とは何でしょうか。
これを明らかにするために「縮退」という新しい概念が導入されます。
縮退とは、例えば「一昔前の商店街ではたくさんの小さな商店や企業が共存して賑わっていたのに、それがだんだん少数の大企業に呑み込まれて、町全体がシャッター街と化している。ところが(中略)必ずしも経済全体が衰退しているわけではない」といった現象です。
また、「世界の経済を見ても、グーグルやアマゾンに代表されるごくひと握りの超巨大企業だけは栄えており、それらだけで統計を取れば世界経済そのものは間違いなく繁栄しているのである。そのため、これが衰退なのか繁栄なのかはひと言では言えないことになり、そこでこういう一筋縄ではいかない状態」を縮退と呼ぼうというものです。
縮退は、生態系の分野では「少数の種だけが異常に繁殖してほかの多数の弱小種を駆逐し、種の寡占化が進んでいる状態」であり、それは「悪い」生態系であるとも説明されます。
このように、「縮退」は巨大企業による寡占化のような現象として理解することもできますが、長沼氏はこの概念をさらに拡張します。
それは「質的な縮退」という考え方です。
19世紀から始まった資本主義の暴走は、資源の消費をともなう量的な拡大でした。
その様子は、経済成長とともに急増する石油の消費量によって象徴的に示されていました。
しかし、石油の埋蔵量は有限なので、経済成長が続くといつかなくなってしまうのではないか、という不安が生じます。
実際に、僕が大学に入ったころ、『成長の限界』という本が世界的に話題になっていて、それによるとこのままの勢いで世界の経済成長が続くと21世紀までには人類は石油をはじめとする地球上のあらゆる資源を使い尽くしてしまって、資源の枯渇とともに滅亡するであろう、ということが予言されていたのです。
ところが、この予言は実現しませんでした。
石油は枯渇するどころかむしろだぶつき気味で、取引価格もかなり下がっています。
石油の消費は心配したほど増えませんでしたが、世界経済は引き続き拡大していて、今では資源の問題以上に環境問題が深刻化しています。
この数十年間で一体何が変化したのでしょうか。
ここで長沼氏は人間の「願望」というものに目を転じます。
人間の長期的願望と短期的願望の対立です。
例えば、健康とタバコの例で言うと、健康は長期的願望で、タバコを吸いたいというのは短期的欲望です。
一般的に、この二つの関係では短期的欲望の方が強力で、長期的願望の方は、注意深く意識的に保護しないと、すぐに短期的欲望に駆逐されてしまいます。
どうやら現代の資本主義経済はこの短期的欲望をひたすら満たすことで富を生み出しているようなのです。
つまり、加速する人間の欲望の短期化が、昔の時代からの伝統や習慣で注意深くコントロールされ、意識的に保護されてきた長期的願望を呑み込んで、駆逐することによって富を生み出しているのです。
このことを長沼氏は「現代の資本主義は量的な拡大よりも質的な縮退で富を絞り出すようになった」と言います。
これが資源の枯渇が起きなかった理由でした。
資源の枯渇が起きなかったのは良いのですが、一方で事態はより深刻な方向に進みつつあります。
「短期的欲望が極大化して、進むことも退くこともできなくなり、回復手段を失ったまま半永久的にそれが続くように」なってしまっているのです。
このような状態のことを長沼氏は「コラプサー」と呼んでいます。
「縮退によるコラプサー化」です。
さて、ここまでに「縮退」と「コラプサー」という二つの概念が出てきました。
これらの概念は実にパワフルで、これが導入できたことだけで長沼氏の「未来の経済学」は成功している、と言っても良いくらいです。
概念というものはぴたっとツボにはまった時には、とてつもない力を発揮するものなのです。
ところで、そもそも「概念」とは何でしょうか。
私たちはビジネスの場でも、よくコンセプトという言葉を使いますが。
野中 郁次郎先生によると、概念とは「新たな視点」のことです。
それは、物事の本質を掴み取ることのできる視点。
これまで見えていなかった、あるいは見落としていた事象を明らかにし、新しい現象を見出す手がかりとなります。*1
そして、そのような概念をつくり出すのが、メタファーです。
野中先生は、数年前に佐藤 明氏と僕がインタビューをさせていただいた時に「概念はメタファーでしか表現できない」と断言されました。
また、
「メタファーはカテゴリーを超えた類似性から飛ぶことです」
とも教えてくれました。
僕はこの「飛ぶことです」という表現が大好きで、これを聞いた瞬間にさっと光が射したように感じたのを思い出します。
それでは、「縮退」や「コラプサー」という概念がどのようなメタファーの方法でつくられているか見てみます。
それはどこから「飛んだ」のでしょうか。
実はブラックホールから飛んできたのです。
縮退は量子力学における用語で、天体がブラックホールになる過程で恒星の中心部が固着して温度調節機能が麻痺し、熱が際限なく中心部に溜まってしまう状態を表します。
「コラプサー」はブラックホールの古い呼び名で、今ではほとんど使われていない言葉だそうです。
予想外に遠くの宇宙から飛んできたのでした。
僕の経験では、メタファーは遠くから飛んだ時ほどパワフルになるようです。
そのことを入山 章栄氏は「知の探索」と呼んでいます。
ビジネスには既存事業の改善や利益創出につながる「知の深化」と、イノベーションや中長期的な成長につながる「知の探索」の2軸が必要ですが、「知の探索」においては既存事業や自分たちの業界からできるだけ遠く離れた場所に探索に出かけることがすすめられています。
自分たちの領域の近くにあるものは、わかりやすく消化しやすいですが、逆に言うと新鮮さに欠けて革新力が期待できないからです。
長沼氏はブラックホールというかなり遠くから飛べたことで、パワフルな概念の創出に成功しました。
それにしても、長沼氏はなぜブラックホールに注目して、このメタファーを選んだのでしょうか。
「この言葉を採用した最大の理由は、語感の絶妙さであり、とにかく経済や社会の場合、それが『縮退してコラプサー化していく』という表現は、語感の点でこれ以上ぴったりしたものを探すのが難しいほどである。」
これは、科学者を自認する人の発言としては興味深いものです。
このメタファーを選んだ理由は何よりも「語感」であると言い切っているからです。
「コラプサー」などというブラックホールの古い呼び名、誰も知らないようなマニアックな言葉をなぜ用いるのかという理由もこれでよくわかります。
理屈ではなく、語感でした。
だって「これ以上ぴったりするものを探すのは難しいほど」でしょう!
というのが著者の言い分で、これこそまさに直観です。
長沼氏は『物理数学の直観的方法』の中で次のように語っています。
「大数学者 オイラーは、証明でわかるだけでは本物ではないと述べています。直観的に理解できてこそ真の数学者と言えるのだと。」
論理や数式に頼ることなく直観的な理解を促すための方法がメタファーなのです。
さて、「縮退」が明らかになったところで、これを止められる力というものは存在するのでしょうか。
この行き詰まった世界の中で、未来につながる経済学は可能なのか
それが第9章の後半のテーマです。
「何か文明そのものがどうしようもなく行き詰まっているというのが、多くの人々の実感で(中略)それはむしろ貧困にあえぐ国よりも、豊かな先進国に住む若い世代で顕著であり、そこで彼らは、生きる目標を見つけるという点において過去のどの世代より難しい状況に立たされており『行くべき道』を失ったまま、有り余る豊かさに取り囲まれ、閉塞感の中で絶望を強いられて、そこからの脱出こそが最大の問題と感じているのである。」
こうした問題は、実は「欲望を満足させる」という経済学の第一原理が、極限まで実現したことで生まれた問題なのです。
ということは、人間は経済学の第一原理だけでは満足していないということになり、何かそれ以外にもう一つの原理が隠されているのではないか、という推測を呼びます。
その隠されたもう一つの原理を長沼氏は、囲碁のアナロジーで解き明かします。
囲碁の「活路を失った石は死ぬ」という性質を応用して、現代の私たちを取り巻く閉塞感、息苦しさの原因と、そこから脱する方法を見出そうというのです。
例えば、囲碁の「石が上下左右に連結している限り、どんなに離れた位置にあってもその活路によって離れた石は生きることができる」というルールを人間精神に置き換えてみると「自分自身はもはや活路は失っているが、自分と精神的につながっている者が元気に活路を持っていることで、精神がそこに希望を感じて窒息しないでいる状態」ととらえることができます。
また、囲碁の「地」の概念、つまり石の内側にどれだけ多くの空白領域を持っているかが勝敗を決める基準になる、というルールを文明や社会に置き換えてみると、ある文明や社会が真に良い状態にあるのかどうかは、地や呼吸口が多いかどうかで判断できます。
こうしたアナロジーから、長沼氏は経済社会を動かすもう一つの力、もう一つの原理があることを示していきます。
それは
「人間は精神的な呼吸口の数を極大化する方向に社会を動かそうとする」
というものです。
そして、未来の経済学は「利益の極大化」という従来の経済学の原理に、新たな原理である「呼吸口の極大化」を加えて、二つの力が反対方向に働いて拮抗するようにすることで、縮退を止められるとしています。
ちなみに、この「息苦しさ」という感覚は、しばらく前に話題になった『ティール組織』という本にも通じるものを感じます。
これはおそらく世界中の人々、若者だけでなく大人も含めたすべての人が抱えている問題で、心から共感するものですが、この感覚を囲碁のアナロジーで説明しつつ、新たな経済学の原理を導き出してみせる手捌きは見事としか言いようがありません。
これこそまさにアナロジーの方法です。
松岡 正剛氏はアナロジーとは「つなぐこと」であり「関係性の発見」であると言っています。
さらに、「我々はアナロジカル・シンキングをしている動物であって、どんな時も常にメタファーを探している存在者なのである」とも言っています。*2
野中先生が近年しきりとおっしゃっているように、欧米流の手法に過剰に適応した結果、分析過多、計画過多、コンプライアンス過多に陥って身動きできなくなりつつある私たちが創造性を高めて新たな価値をつくり上げていくためには、今こそ直観的方法が、とりわけメタファーとアナロジーの方法が求められているのではないかと思います。
*1 『直観の経営 「共感の哲学」で読み解く動態経営論』 | 野中 郁次郎、山口 一郎(著) | KADOKAWA
*2 『千夜千冊エディション 編集力』 | 松岡 正剛(著) | 角川ソフィア文庫