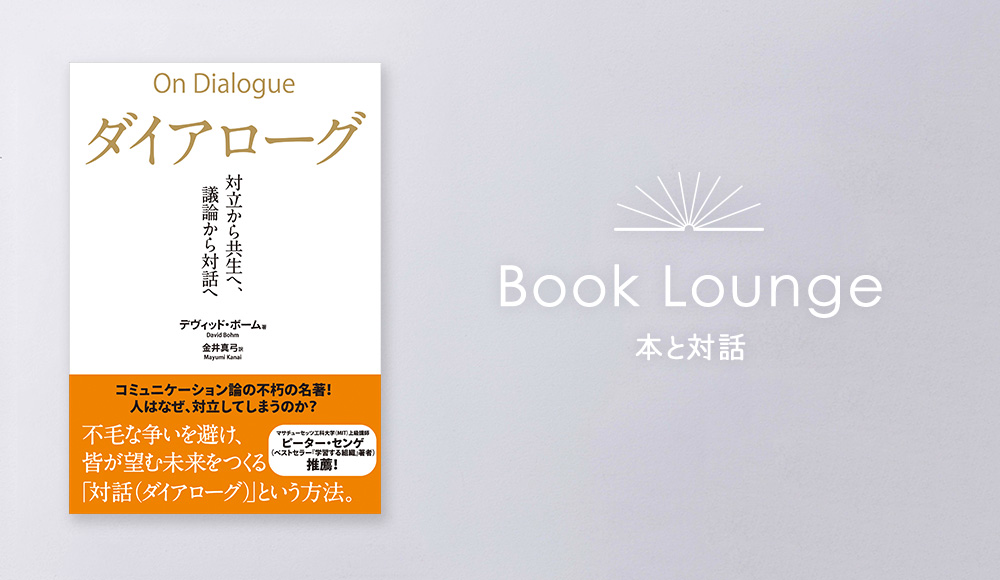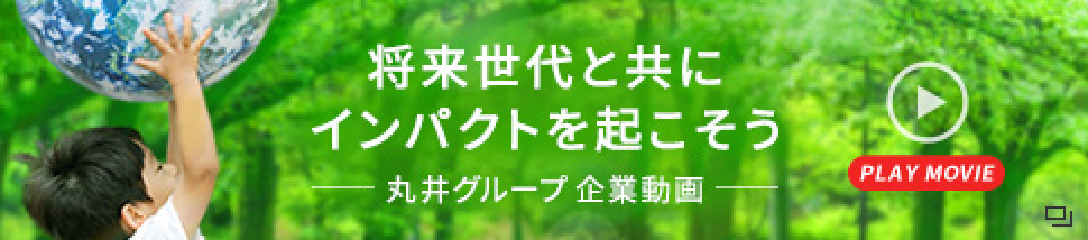#007 世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学

近内 悠太(著)

withコロナにおいて読まれるにふさわしい哲学書
前回ご紹介した本のテーマと関連しつつも、withコロナの現在にふさわしい本は何だろうとつらつら考えていました。
そんな時、(株)エッジ・インターナショナルの永田 洋さんがヒントをくれました。
それが本書です。
永田さんは大変な読書家で、読みたい本を常に手元に置いておきたいという理由で、移動中も10冊近い本をバッグに入れて持ち歩いているそうです。
それほど熱心な読書家の永田さんですから、僕が次に何を取り上げたら良いか迷っているのを見て、そっとヒントをくれたのだと思います。
奥付を見ると2020年3月13日発行とあります。
まさにコロナ禍の只中です。
この時期に出版されたのは偶然としても、本書はwithコロナにおいて読まれるにふさわしい一冊だと思います。
加えて「資本主義のもたらす息苦しさをどうしたら解消できるか」という前回の「本との対話」(#006-2)の問いにも答えてくれます。
そのことは『資本主義の「すきま」を埋める倫理学』というサブタイトルに表されています。
このように述べると何か難しい本のような印象を与えるかもしれませんが、難しいテーマにもかかわらず楽しくて読みやすくなっています。
まるで東野 圭吾のミステリー小説を読むような感覚で、さまざまな伏線や、謎解きをたどりながらクライマックスに向けて一気に読み進んでしまいます。
同時に哲学的な深さもあります。
ですから、最初はおもしろさに任せて一気に読み終えてしまったあとで、落ち着いてもう一度ゆっくりと読んでみることをおすすめします。
スローリーディングです。
なぜスローリーディングなのか。
それは、「資本主義のもたらす息苦しさを解消するには?」といった一筋縄では行かない問いに答えるためには「そもそも資本主義とは何か」といった本質的な問題を考えてみることが必要で、こうした「そもそも・・・とは何か」というような問いかけは哲学の領域に属するからです。
ビジネスに携わる人で日常的に哲学書を読む人は(僕のような変人を除いて)ほとんどいないと思いますが、およそ哲学書というものは東野 圭吾の対極にあって、超スローリーディングでないと読めません。
大げさに言うと5行の文章を読むのに平気で1時間くらい要したりします。
そんなバカな、と思われるかもしれませんが「そもそも・・・とは何か」といったような普段は考えないことを考える時の時間感覚は、日常的な時間の感覚とはかなり違うのです。
哲学の扱う本質というものは、日常生活という表面のだいぶ奥の方に隠れているので、表面から深みへ、起源へと順を追って根気強く論理をたどって行かなければなりません。
aの本質を理解するためには、まずbを理解することが必要で、bを理解できるとcに進むことができて、cをクリアするとdに行き着けて、dを理解できるとようやくaの理解にいたる、といったような長い道のりを根気強くたどる必要があります。
これが、スローリーディングが必要な理由です。
資本主義に限らず、民主主義も気候変動も、現代の私たちを取り巻く問題は一筋縄では行かない問題ばかりです。
近年、ビジネスに携わる人にも哲学の素養が必要だなどといわれるのは、このような課題に答えるためには、時に立ち止まって「そもそも・・・とは何か」ということに時間をかけてゆっくりと考えてみることが不可欠になってきているからかもしれません。
本書はエンターテインメントとして楽しめる一方で、哲学的な本としてもじっくり読めるので、ファスト&スローで二度味わってみていただきたいと思います。
ところで、
本書の魅力は、驚くほど多様な本からの自由自在な引用にあります。
そのことは、表紙からもうかがえます。
表紙の上段と下段に、ウィトゲンシュタイン、テルマエ・ロマエ、シーシュポスの神話、トマス・クーン、ペイ・フォワード、内田 樹、小松 左京、東 浩紀、シャーロック・ホームズ、アルベール・カミュ、星 新一、岸田 秀、メンデレーエフ・・・・・・といった固有名詞が綿々と書き連ねられています。
この羅列は本好きの人間から見てもかなりアットランダムで、これらが贈与というテーマとどのように関係しているのか、想像力をかき立てられます。
読み始めてみると、一つひとつが引用されるたびに、まるでジグソーパズルのピースが然るべき場所にはまっていくように次々と鮮やかな絵柄が現れ、やがて全体像が浮かび上がってきます。
初めに読んだ時には、その引用の多彩さと絶妙さに驚かされるばかりでしたが、二度目にゆっくり読んでみると、引用されていた数々の本たちが、実は本書のテーマである「贈与」そのものであった、ということに気づかされます。
というのもあらためて考えてみると、私たちが考えることや、書き記すことに0から1を生み出すような完全なオリジナルというものはあり得ないからです。
私たちの考えや、私たちの書くものは、私たちが意識している以上に、これまでにさまざまな人たちが考え、書き残してきたこと、つまり本から影響を受け、形づくられています。
表現の仕方には違いが見られるにしても、内容的には純粋にオリジナルなものは存在せず、多くは先人たちに依っているのです。
その意味で、本書は贈与というテーマを論ずるに当たって、数多くの本を引用することで先人たちの贈り物に対して感謝を表すという、正にテーマにふさわしい方法が用いられていると言えます。
そうした引用の中でも際立っているのがSF作品です。
二つのSFが紹介されています。
一つは小松 左京の小説。
小松 左京はおもに1960年代から70年代にかけて活躍したSF作家で、『日本沈没』などの作品があります。
日本三大SF作家の一人ともいわれていて、僕よりも上の年代の方にはなつかしい名前ではないでしょうか。
とりわけ『復活の日』(1964年)はパンデミックによる人類の滅亡を描いた作品という点で、コロナ禍の現在にあっては見過ごせない作品です。
この時期にこの作品が引用されていることは、シンクロニシティとしか言いようがありませんが、実はそのことが思いがけない効果を生んでいます。
というのも、今回のコロナ禍は人類の命を脅かす脅威であると同時に、ある意味でSF的な側面を持っているからです。
どういうことでしょうか。
小松 左京氏は、SFとは「現実にはないこと」つまり「常識では考えられないこと、普通でない、異常・異様なこと」を描く小説である、と言っています。
そして、「たった一つの歯車を狂わせただけで、私たちの日常は激変し、悪夢へと変わってしまう。SFはそんな世界の歯車を狂わせる物語形式」だと言います。
ウイルスという目に見えない脅威によって突然、日常生活が一変し、外出や通勤・通学が制限され、移動ができなくなって家に留まらなければいけない、というコロナ禍の状況はまさに小松 左京氏の言うSF的な状況ではないでしょうか。
ところで、SFはなぜわざと歯車を狂わせてみせるのか。
それは、私たちが「この世界と出会い直すため」だと著者は言います。
私たちが「忘れてしまっている何かを思い出させる」ためなのです。
どういうことでしょうか。
そのわけはもう一つのSF作品が教えてくれます。
『テルマエ・ロマエ』です。
この漫画は映画にもなったので、ご存じの方も多いと思います。
主人公である古代ローマ人のルシウスは浴場の建築家ですが、なぜかことあるごとに現代日本のお風呂や銭湯にワープしてしまい、そのたびに銭湯のプラスチック桶やシャンプーハット、フルーツ牛乳など古代ローマにはない文物に触れて驚き、感動して、何とかそれらを敬愛するハドリアヌス帝やローマ人たちに伝えたいと奮闘します。
私たちにとっては当たり前の物事を見て、大げさに驚いたり、感動したりするルシウスに、私たちは思わず笑いを誘われます。
ところで、このお話のどこがSFなのでしょうか。
著者は「ルシウスがこの世界(私たちの生きている現代の日本)と初めて出会う姿を見て、私たちはこの世界と出会い直す」と言います。
ルシウスを通じて世界と出会い直すことで「私たちには実は多くのものが与えられていたことに気づく」のです。
何気ない日常の中には無数の贈与のありがたみが隠されています。
「それらはあって当たり前で、なければ僕らは文句を言う。コンビニの陳列棚の商品、自販機、部屋の空調設備、電車の定時運行、あるいは衛生環境やインフラ、医療—」
このように、私たちは何かがないことには気づくことができますが、何かが「ある」ことにはなかなか気づけません。
ルシウスは現代を生きる私たちに何が与えられているかを教えてくれる、古代ローマからの「贈与のメッセンジャー」だったのです。
このように、私たちはSF的な想像力を通じて「世界と出会い直す」ことで実に多くのものが与えられていたことに気づきます。
今回のコロナ禍はSF小説ではなく、現実の災禍ですが、その中で実際にコロナに感染してしまったことで「世界と出会い直す」ことができたリーダーがいます。
英国のボリス・ジョンソン首相です。
医療従事者の手厚い治療、看護と自ら馳せ参じた多数のボランティアの人たちの献身的な支援によって生還したボリス・ジョンソン氏は、
「コロナが証明したことがある。それは『社会』ってものがあるということだ」
と国民へのメッセージで述べました。
この発言はサッチャー元首相の「社会なんてものはない。あるのは自分と家族だけだ」という有名なネオ・リベラル宣言への決別であると解説されています。*1
僕はこの言葉にルシウスの眼差しを感じます。
それは、この世界には医療従事者やボランティアの人たち、さらには生活に必要なものを届けてくれる運送業の人たちや、食品スーパーの人たちなどがいて、私たちの生活を、社会を支えてくれている、コロナ禍によってそのことに気づけた、ということです。
私たちはこれまで経済的、物質的には恵まれながらも何とも言えない息苦しさ、何か大事なものが欠乏しているような感覚にさいなまれてきました。
それは、お金で買えるものに恵まれすぎたために、あらゆるものがお金で買えるかのような錯覚に陥ってしまい、お金で買えないものが見えなくなってしまったからではないでしょうか。
コロナ禍は「世界の歯車を狂わせる」ことで、私たちにもう一度「世界と出会い直す」機会を与えているように思います。
もしこの機会に私たちがお金では買えないものとしての贈与、すなわち人と人のつながりや、信頼、尊敬、感謝、献身、愛などを再発見し、これまで以上に大事に育むことができれば、私たちは息苦しさを超えて新しい社会、経済をつくり出していけるかもしれません。
*1「『強い社会』が決する国々の興亡」船橋 洋一(文)文藝春秋2020年7月号