「あたりまえを超える」体験を生み出し続けるために
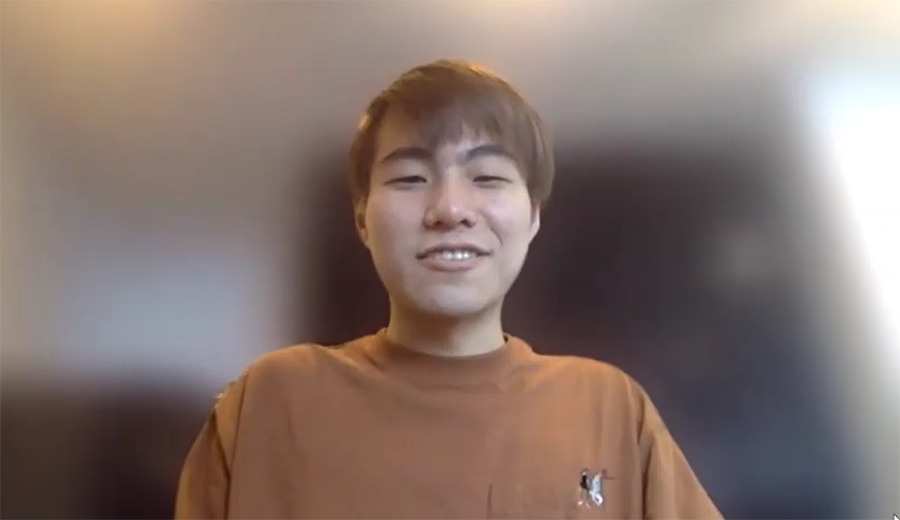
丸井グループでは、今後の経営にとって重要となるさまざまなテーマを考える場として「中期経営推進会議」をほぼ毎月開催しています。
2021年2月5日(金)、「『あたりまえを超える』体験を生み出し続けるために」というテーマで、丸井グループとの取り組みを進めているWED(株) CEOの山内 奏人さんの講演と、青井さんとのトークセッションをオンラインで行いました。
幼少期からプログラミングに興味を持ち、15歳で起業したWED(株) 代表取締役の山内 奏人さんにご登壇いただき、ご自身の生い立ちや「魔法を社会に実装する」会社の方針についておうかがいしました。当社代表の青井とのトークセッションでは、テクノロジー以上に重要視しているデザインについてや、若手起業家が大企業との共創に求めることなどをお聞きしました。
WED(株) 山内 奏人さんによるプレゼン
非日常を実装する「世界観ドリブン」なサービスづくり
僕はWED(株)という会社の代表として、「魔法を社会に実装する」ような仕事をしています。例えば、「紙がお金になる世界」。僕たちが開発した「ONE」というアプリは、レシートを写真に撮るだけでお金がもらえる、まさに、「紙がお金になる」体験です。取得したレシートをデータ化し、企業の販売促進や分析に役立ていただく仕組みです。実は、これは「紙に金額を書きこむとお金になる」というドラえもんのひみつ道具「円ピツ」から着想を得てつくりました。このサービスで、今までゴミになっていたレシートが、まるでゲームのようにワクワクするものになったのではないでしょうか。このように、僕たちは世界観を考えてから、ビジネスモデルをつくっています。その順番のほうが再現性は低いかもしれませんが、利用者の最大化をめざすことができるので、事業を成長させやすいのではないかと思います。
僕は小学生の時、変化が怖くて、保健室に登校したり、学校にあまり行けなかったのですが、プログラマーになり、中学校・高校へ通いながらエンジニアとして働いてきました。その後、さまざまな会社を転々とし、2015年に創業のきっかけになるような事業をつくりました。2016年にWEDを創業して、資金調達と事業のスクラップアンドビルドを繰り返し、2018年に、この「ONE」というサービスをリリースしました。2019年に初めて売上を出し、2020年にようやく年商の桁が1つ上がりました。
世間一般では、創業者の実体験に基づいてサービスをつくる「実体験ドリブン」が正義とされていると感じます。確かに、その業界について理解があるという利点はありますよね。ですが、僕は「実体験ドリブン」ではなくて、「世界観ドリブン」を重視しています。これは、保健室登校や、会社を転々としたり、事業を潰したりという、いわゆる「青春」といわれる期間を苦しく歩んできた人生から、「おもしろい」「楽しい」というような「非日常」な体験を実装したいと思ったからです。ディズニーランドや映画館、美術館のように、「自分の得意分野である、テクノロジーとデザインを使って、非日常体験のつくり手になりたい」と考えています。
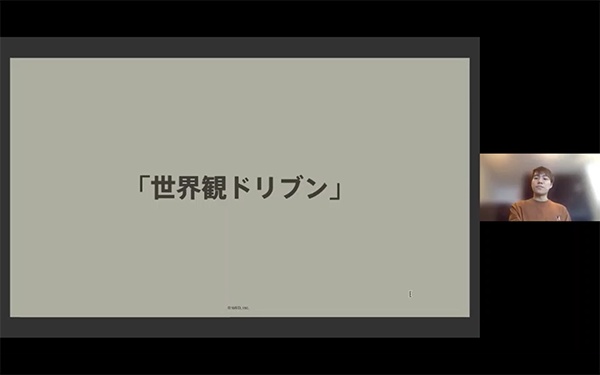
「魔法を社会に実装する」ために
ここまでは割とHOW(どうやるか)の話をさせていただきましたが、ここからは「何をやりたいのか」という話をさせていただきます。
昨年、5年目にして会社のテーマを「未来の消費を追求する」に定めました。日常というのは消費によって成り立っていて、つまり「未来の日常を想像し続け、非日常の追求をすることによって未来の日常をつくり出していく」ということです。今は、既存の事業のグロースやクライアントさんとの協業を進めています。先ほどお話しした「ONE」だったり、丸井さんと協業している売上管理のソフトウェアサービス「Zero」ですね。今、20人ほどいる社員の内の4人で担っている「ラボ」という組織では、新規事業などの技術開発をしています。
今、僕らは未来の消費の中でも三つに軸を絞っています。一つはキャッシュバック消費。これまではモノ自体がディスカウントされていましたが、それをユーザーに還元する動きが、今後伸びていくと考えています。次に、エシカル消費。社会課題解決に結びつく消費ですね。三つ目が、積立型消費。流行のサブスクリプション型はあまりサステナブルではないと考えているので、積立型の消費体験をテーマにしています。
僕たちの考えるマクロ的な消費者関連市場の変化は、四つです。一つ目は、オンラインとオフラインが溶けていくこと。広告の市場が大体3兆円あるのに対して、OMO領域での販促市場は、現在、およそ15兆円に伸びています。例えば資生堂さんでは、媒体費に占めるデジタル比率を50%から90%、100%まで引き上げる宣言をされています。コロナ禍の影響もあって、WEDでも販促の支援案件が大きく増えています。二つ目は、オフラインの購買データの重要性が上がること。現在、購買のオフライン比率はまだ94%くらいあって、オフラインもまだまだ重要視されています。三つ目は、巨大消費者関連企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)で、今後10年で3.8倍に成長すると言われています。四つ目は、新興世代は特にモノ消費からコト消費にますます移っていくということ。この四つの軸で僕たちは事業を考えています。
2020年は、キャンペーン事業や、ユーザーから集めたデータを起業に提供する事業をしてきましたが、徐々にソフトウェアサービス事業を開始したり、今年はメディアをオープンするなど、2022年、2023年は、もっと広告運用やマーケティング、消費財、パーティカルマーケット*¹プレイス事業まで展開していけたら良いなと考えています。この先たくさん事業を起こしてたくさん失敗すると思いますが、全社をあげて頑張っていきたいです。
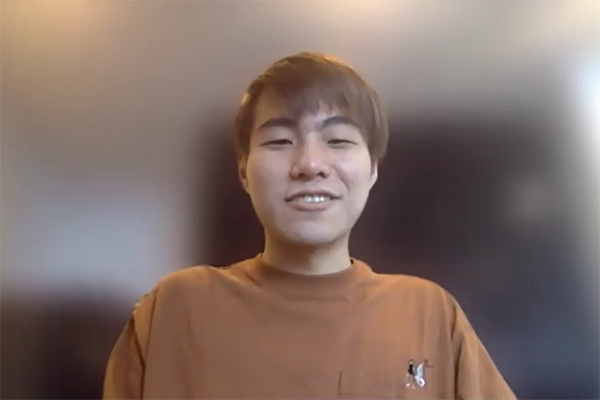
*¹ バーティカルマーケット:金融・保険・運輸・医療など、一定の業種に特化した市場。
山内さんと当社代表 青井のトークセッション
デザインとテクノロジーの補い合う関係
青井:山内さんのプレゼンテーションがすばらしくて、感動しました。20分ってプレゼンとしては比較的短い時間ですよね。
山内:そうですね。もともとは40分いただいてたんですけど、せっかく青井さんとお話しさせていただくなら、ぜひインタラクティブな時間を長めに欲しいとお願いしました。
青井:深く共感します。社外で登壇させていただく際に、親切心で時間を長く取っていただくことがあるんですけど、1時間半も話すことってないんですよね。なので僕も、「むしろ双方向でやりたいので、プレゼン時間はもっと短く、20分くらいにしてください」とお願いすることが多いので、考えが一緒でうれしいなと思いました。もう一つ感動したのは、プレゼン資料のデザインです。山内さんも「デザインとテクノロジーが自分の強み」とおっしゃっていましたが、文字で理解しやすくてとても良いですよね。プログラミングは独学だそうですが、デザインはどうやって学ばれましたか。
山内:プログラミングというのは結局、プロダクトをつくるためにあるものなんです。昔は、より良いプログラミングやアルゴリズムを書くことにひたすら注力していたのですが、ある日ふと、プログラミングで改善するよりも、デザインをこだわる方が良い物ができるんじゃないかと思い、そこからデザインの勉強を重視するようになりました。
青井:では、デザインも独学なんですか。
山内:そうですね。今も別にデザインが得意というわけではないですが、すごいデザイナーの方や、デザインに長けた社内の人間とお話しする中で磨いていったという感じです。
青井:デザインって単に見た目の良さというイメージがありますが、内容がよく伝わるというのが重要なところだと思います。山内さんのプロダクトは見た目と中身が一致していて、とてもすばらしいなと思いました。
山内:ありがとうございます。
青井:資料のつくり方って、世代によってすごく差が出るなと感じます。例えば、年齢が上になればなるほど、書類をそのまま映しているような、文字量のある資料が多いです。でも、中学生・高校生くらいになると、文字が本当に少なくて、写真や映像だけに言葉が乗っかるものが多い。でも今日の山内さんのプレゼンは、割と文章が多かったですよね。
山内:理由は二つあります。一つは、高橋さんという有名なプログラマーが提唱している「髙橋メソッド」です。PowerPointをプログラミングして動画のように伝えるというこのメソッドを、僕も使わせていただいています。もう一つは、ミレニアム世代以降というか、1995年生まれ以降の人たちは、集中力が8秒ぐらいしか持たないらしいんです。僕もそういうところがあるので、入れ代わりや動きのあるプレゼンを意識しています。
青井:なるほど、そういうメソッドがあるんですね。プレゼンの中で「まずシンプルにワクワクすることからスタートして、ビジネスモデルは後付けで良い」っていうお話がとても印象に残ったんですけど、なぜでしょうか。
山内:インターネットビジネスに限ったことではないですが、今は人が集まれば収益化できる時代になってきていますよね。僕がプロダクトを何回も潰しているのも「人が集まらなかった」ということが大きいです。イーロン・マスクが、議論が進まない時に、誰もが「そうだよね」って思うことをベースに物事を進めていくという「第一原理思考」(first principles thinking)を推奨しています。僕も「サービスが使われない」という問題に対して、「誰もが使ってみたいもの」を考えた時に、「『ドラえもんのひみつ道具』をどうにかしてつくり出せないか」とひらめいて、結果として1週間で約30万人に使っていただけました。ビジネスモデルは後付けで、リリースしてすぐに30万人に使われるサービスはほとんどないのですが、「第一原理思考」によって圧倒的に早く規模感を出せるようになったという自負があります。
青井:すごくおもしろいですね。当社も協業を目的としたスタートアップ投資を始めて、これまで会わなかったようなジャンルのファウンダーとお会いしたりするんですけど、山内さんが今おっしゃっていたことをとても実感します。ビジネスモデルがよくできてるなと思っても、なんとなく投資したくない会社もありますが、一方で、ビジネスモデルはシンプルで別に驚くことは何もなくても、話を聞いてすごくワクワクして、とにかくここに投資したい、一緒にやりたいというところがあります。社内の新規事業でも同じで、ビジネスモデルがしっかりしていても、「ワクワクするアイデアが出てくるまで、もう少し考えてみようよ」ということがあります。

将来世代が大企業との協業に求めること
青井:ちょっと話題を変えまして、山内さんとの出会いから、丸井グループとの協業に至るまでを振り返ってみたいんですけど、確か最初にお会いしたのって4年ほど前ですよね?
山内:いや、もっと前ですね。僕が多分中学1年生ぐらいの時。
青井:だいぶ前ですね。そのときにもうすでに子ども向けの教育アプリを実装されていましたよね。しばらくしてから「最近何してるんですか」ってお聞きしたら、「フィンテックをやっています」と言われて、すごくびっくりしたことを覚えています。教育からフィンテックへというのは、どういうきっかけがあったんでしょうか。
山内:例えばアメリカって、Facebookのマーク・ザッカーバーグや、Snapchatのエヴァン・シュピーゲル、Twitterのジャック・ドーシーというような、トップ企業のビジネスマンに元エンジニアの人たちがいるから、子どもたちも憧れると思うんですけど、僕は別にヒーローではないし、エンジニアとして有名でもないと。だから、僕が「プログラミングは楽しい」と言っても説得力がないと思ってたんです。
そのころにたまたま出会った投資家の方が、毎日違う事業アイデアを進めていたんです。例えば、「昨日アメリカで資金調達のリリースが出たスタートアップの事業モデルを、日本に持ってきたらどうなるか」みたいことを、毎日組み立てていて。僕たちの世代って、やり切れていないことが枯渇している時代なんです。大手のベンチャー企業も多い中で、何の分野が残っているかを考えて、僕らの世代が一番使うであろうサービスをつくるのは楽しそうだなと思って、残っていたフィンテックを選びました。
青井:なるほど。すごくおもしろいですね。起業する際、テクノロジーとの間の取り方ってすごく重要だと思うんです。以前、山内さんに「ブロックチェーンについてどう思いますか」とお聞きしたときに、「実装されるのは10年ぐらい先になると思うので、今、それを使うよりも、その前にできることがあるんじゃないか」というようなことをお話しされていましたよね。そのころは、「仮想通貨ではなく、ポイントを通貨として使う」という方向でビジネスをされていたと思います。「どういうテクノロジーをどのタイミングで実装するか」ということを試行錯誤されてきたと思うんですが、経緯や向き合い方について、お聞きできますか。
山内:僕たちは、プロダクトをつくる時に三つの要素を決めます。一つ目は、ストーリー。これはもう圧倒的に大事で、「何のためにやるのか」「どうやるのか」ということ。二つ目は次に大事なデザイン。「どういう見せ方をするのか」「どう世の中にインストールするのか」ということですね。そして三つ目が「どう実現するか」というテクノロジーです。プロダクトにおいてはテクノロジーよりもストーリーやデザインの方が、圧倒的に大事だと考えています。なので、デザインやストーリーの話を抜きにして「ブロックチェーンはすごいテクノロジーだ」と言われても、極論、「だから何?」っていう話で。「ブロックチェーン」という言葉だけが先走りしていくと、それが本当に適切なテクノロジーなのかが、わからなくなっちゃうんですね。それは、すごくもったいない。
「デザインは、この社会ではまだ実現できないことも描けてしまう。それをいかに問題なく実装するかがテクノロジーの力だ」と、うちのエンジニアはよく言います。だから僕も、テクノロジーは守りだと思っています。
青井:今、そのように言われてみると、本当にそうだなと思います。去年から、丸井グループとの協業を模索していて、先ほど話に出た「Zero」という、商業施設のテナントの売上管理をDX化していくシステムを開発していますよね。どんな経緯を経てこの事業にたどり着いたのですか。
山内:丸井さんにヒアリングした際、「店舗のオペレーションが電子化・データ化できなくて困っているから、何か一緒にやりたい」とお話をいただきました。普段は僕ら側から提案をするんですけど、逆に提案をいただけて本当にうれしかったです。うちはプロダクトの会社で、最初は、ある種受託開発のようになるので、外からアイデアを持ち込んだ経験がなく、開発には結構悩みました。
でも、今の市場ではSaaSの会社が圧倒的に強くて評価額がつくような状況にあるんです。だから「ユーザー向けのサービス」が弱っていて、それこそスタートアップ業界は二項対立みたいな状況になっているんですよ。SaaSの方がビジネスモデルがわかりやすくて、資金援助も受けやすく、逆にtoCのサービスにお金がまわらない。「僕らはどうするべきか」と悩んでいたところ、「その課題はどんな商業施設も持っているから、拡げていけますよね」と、恥ずかしながら僕らからではなく、丸井さん側から提案していただきました。丸井さんと共同開発するプロダクトがあるからこそ、「ONE」というC向けのサービスが伸びていく。金銭面でも、テクノロジーでも、両方が両社を助け合う。それでこそ二項対立を解消できるのではないかと気づきました。これは絶対にやりたいと感じて、社員や役員、株主の方々にも、同意をとって、事業展開という形にさせていただきました。
青井:葛藤があったのは全然知らなかったので、驚きました。でも、株主さまを含めて賛同していただけたことがありがたいなと思います。今はBtoB的なお付き合いですが、今後はレシートなどのオフラインでのデータでも協業を重ねていきたいです。
山内:はい、よろしくお願いします。
青井:私たちは、これからの世代のスタートアップの皆さんと一緒にビジネスをすることで、未来をつくっていこうとしているのですが、山内さんたち若手の世代が、大企業との協業で求めることはありますか?
山内:僕らからというより、若手の世代からという形でお話しさせていただきますね。僕は、2017年、16歳のときに1億円の資金調達をしました。投資家サイドからすると、16歳に1億円を投資するって、まあまあクレイジーなことですよね(笑)。当時、僕は18歳以下で会社の代表にはなれなかったので、その投資家の方に代表取締役をやっていただいたんです。それくらいハンズオン*²してくれる投資家の方に出会えたことが、一番ありがたいことだと思います。若いと褒められるのはうれしいことなんですけど、反面、下駄をはかされることも多くて。起業家って、事業によって成長させられると思うので、事業の実績や、起業家の想いをきちんと見て協業を決めてほしいと思います。僕も当時はむやみに持ち上げられることもありましたが、その投資家の方は、僕のことを見て意思決定されていたと感じていました。
青井:それは年齢を超えて付き合うということでしょうか。僕も、年々、年齢ってあまり関係ないなという思いがすごく強くなってきています。その人の発言や行動、考えとまっすぐに向き合っていくのがお互いに良い関係だと思います。ビジネスの場では特にそういう、フラットに年齢を超えたお付き合いができると良いですよね。
山内:はい。おっしゃる通りですね。
*² ハンズオン:投資を行う際に、その後どの程度マネジメントに関与するか

長く伴走するための「共創投資」
青井:山内さんの会社では、(株)グッドパッチの土屋社長を社外取締役に迎え入れられましたよね?これから成長するにあたって、すでに上場された起業家のノウハウが必要だと感じてらっしゃると思いますが、経緯や、期待していることについてうかがえますか。
山内:もともと、僕が住んでいたマンションに土屋さんも住んでいで、そこですごく仲良くなりました。グッドパッチさんも同じくプロダクトをつくる企業で、クライアントさんやユーザーさんや株主の方とか、自分たちの家族とか、ステークホルダーが多い事業をされています。その中での動き方が勉強になると感じたことが理由の一つです。また、日本では早く上場することがあまり良くないという雰囲気がありますが、Goodpatchさんは早めに上場することを決定した会社なんです。それも、日本で割と小さく上場して、 そこから伸ばしていくというスタイルを取っていて、しかも、コロナ禍のど真ん中で上場されているんです。遅らせることはせず、できるだけ早くメジャーに行くというか、大きい市場で戦うと決めている。デザインの思想を持っていて、本当に兄貴のような存在なので、一緒に戦って行きませんかとお願いしました。
青井:ということは、山内さんもどちらかというとユニコーン型というよりは、早くIPOして、そこからさらに成長していきたいという考えなんですね?
山内:はい。日本では、未上場の市場には投資家がとても少ないと思います。日本のベンチャーキャピタルって、50社くらい会うと大体網羅できちゃうんですよ。なので、できるだけ早く大きい市場で、それこそメジャーで戦いたいという考えがあります。
青井:それは私たちにとってもすごく良い話です。というのは、ベンチャーキャピタルって、企業が上場したり、大手に買ってもらったりしたところで現金化してしまいますよね。でも「共創投資」と呼んでいる我々の投資スタイルでは、協業が前提になっているので、協業が続く限りはずっと株を保持するスタンスなんですね。ファイナンシャルリターンの視点では、上場したあとも成長して価値が上がると、我々のリターンも大きくなります。例えば、BASEさんも上場してから株価が10倍ぐらいまで上がっていて。今、おっしゃられたように、日本もVCは結構ありますが、上場後もしっかり投資するスタイルのところは多くないので、もう少し長い時間伴走していくような関係をつくりたいと思っていたので、勇気づけられる感じがしました。ありがとうございます。
最後に一言だけ、私たち丸井グループに期待することがありましたら、教えていただきたいです。
山内:丸井グループの将来世代との協業には、すごく期待しています。今はなんだかんだ若者が起業しない、起業してもスケールのある事業にならないことが多い。僕のまわりでも、最近は起業する人が増えてきましたが、受託開発やフリーランスなどが多くて、事業を起こす人は多くないです。なので、丸井グループではアクセラレーターなどもされていますが、これからもぜひいろんなリソースを買ってほしいと、僕ら世代からは思います。
青井:ありがとうございます。本当に、将来世代との共創に全力を注ぎたいと思っているので、今のお言葉もしっかりと受け止めてやっていきたいと思います。ありがとうございました。
- 登壇者プロフィール
- 山内 奏人氏
WED(株) 代表取締役CEO 2001年、東京都生まれ。
小学生の頃からPCに親しみ、プログラミングを独学。 小学6年生の時、「中高生国際Rubyプログラミングコンテスト」の15歳以下の部で最優秀賞を受賞。 2016年にWEDの前身を立ち上げ、2018年にレシート買取アプリ「ONE」をリリース。




















