Withコロナの時代こそWell-beingが「しあわせ」をつくる(後編)
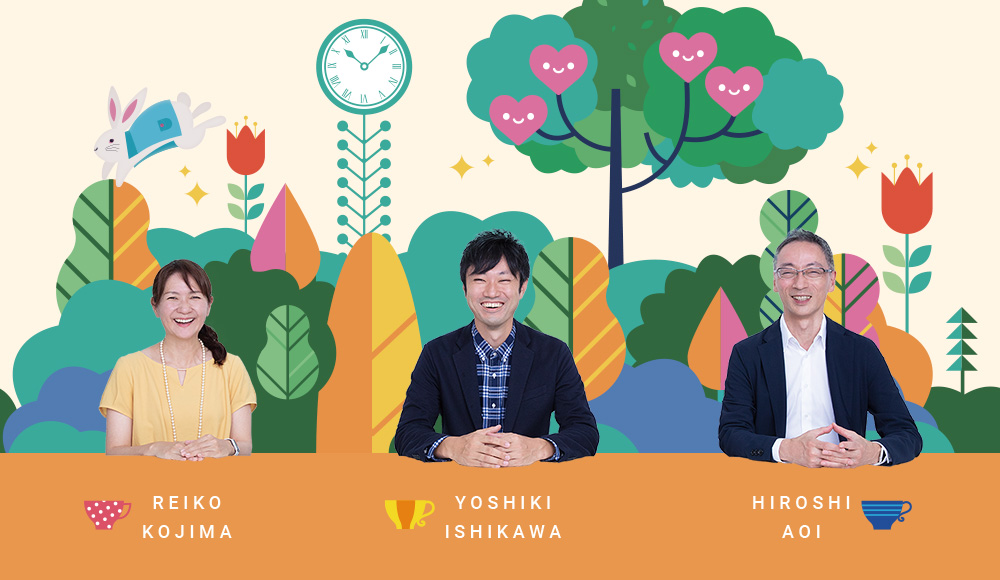
-
- 小島 玲子
- 株式会社丸井グループ 執行役員
ウェルネス推進部長 兼 専属産業医
-
- 石川 善樹氏
- 医学博士
公益財団法人Well-being for Planet Earth 代表理事
株式会社丸井グループ アドバイザー
-
- 青井 浩
- 株式会社丸井グループ
代表取締役社長 代表執行役員 CEO
「良くある、良く居る」ことを意味するWell-being(ウェルビーイング)。コロナ禍により、私たちが従来の価値観の見直しを迫られる中、重要なキーワードとして注目されています。2020年7月、当社のアドバイザーに就任した、Well-being研究の第一人者である石川 善樹氏と当社の青井、小島が、新たな時代の「しあわせ」のつくり方を語り合います。
ミレニアル世代に浸透する価値観とは
青井:2019年くらいから「ステークホルダー資本主義」ということがいわれるようになってきて、従来は株主への貢献を優先していたのが、関連するすべてのステークホルダーに貢献すべきという価値観に変わってきました。それでは、すべてのステークホルダーの利益とは何なのかと考えた時、「金銭的利益だけで満足する人はどのくらいいるのだろう?」と思ったのです。もちろん、金銭的利益で応えることも必要なのですが、お金で測れないものも期待されています。それは、ミレニアル世代の6割が企業に利益の追求よりも、社会課題の解決を望んでいるという点にも表れています。株主資本主義の時とは明らかに異なる価値観が、ここ数年で急速に広がってきています。その辺が、Well-beingが注目され始めた背景なのかなと思っています。
石川:あくまで私見ですが、Well-beingが日本でいわれ始めたのは、せいぜいこの2年くらいです。最初のころは「なんじゃそれ?」という反応でしたが、一気に広がっています。おそらく世代交代が一気に進んだということでしょう。いわゆるミレニアル世代が株主やベンチャーキャピタルにも入り始めています。日本でも2025年くらいには、ミレニアル世代が社会の中心を占めるようになります。彼らが小さいころから馴染んできた価値観は、「サステナビリティ」とか「ダイバーシティ」、さらには「Well-being」なのです。
青井:今まで名づけられていなかった、もう一つの価値観がWell-beingですね。
石川:今までは「良い人生=良い会社=良い学校」だった。僕はそういう価値観のぎりぎり最後の世代で、僕の下の世代は、自分なりの良い人生を見つけることに重きを置いている人が多いです。「何としてでも金持ちになってやる」みたいな人はたぶんほとんどいないと思います。金持ちにならないと手に入らないものが今はあまりないのです。
青井:お金で買える物質的なものには満たされていても、逆にお金で買えないものへの飢餓感がすごくある気がします。僕は何となく「息苦しさ」と呼んでいるのですが、息苦しさから解放されて自由に空気を吸いたいという気持ちが、飢餓感みたいなものとしてあると思っています。そうした世代の欲求と関係があるのかもしれないですね、「ダイバーシティ」とか「サステナビリティ」とか「Well-being」というものは。
石川:これまでは、資本主義は絶対的な正義だったのですが、今の子どもたちにとっては、たぶんそうではないんでしょうね。では、何が正義なのか。昔はより高価なものが求められたのですが、今はより適正なものが求められていますよね。例えば、僕が今注目している企業に、台湾のオーライトという会社があります。
青井:有楽町マルイに出店していただいています!
石川:オーライトの歯磨き粉は、1本約3,200円。初めは「高い!」と思ったのですが、100%循環型で環境にも健康にもめちゃくちゃ優しい。すべて食べ物からつくられているのです。そういう話を聞いていくうちに3,200円が普通で、僕が知っていた今までの歯磨き粉は、逆に安すぎるんだと視点がガラリと変わりました。これから人は、よりサステナブルで、より適正なものにどんどん流れていくと思います。
青井:そこはすごく重要かもしれない。サステナビリティ経営における最近の一番大きな出来事は、フランスのダノン社が「Entreprise à Mission(使命を果たす会社)」を揚げて、定款を書き換えたことです。フランスでは会社法自体が株主利益の追求だけではだめだというふうに変わり、その法律変更を受けてダノン社は、定款を変えたのです。取締役会とほぼ同じ位置づけでミッション委員会を設け、株主利益に反することをやりたい場合には、その委員会で決議しなければいけないという建てつけに変更したのです。
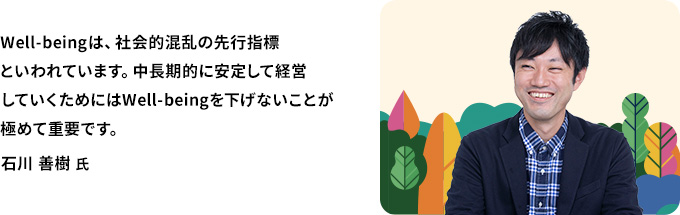
社会も企業もWell-beingを下げないことが重要
小島:先ほどの世代交代という話はなるほどと思いました。この2年で3人の新入社員に、「ウェルネス経営推進プロジェクトに入りたくて入社しました」と言われたのです。
石川:すごいですね。この間もある会社で、一時在宅勤務になって、これからどうするかという話をしている時に、ある若い社員が「妥当な理由があれば出社しますけど、いかがですか」と社長に聞いたらしいのです。会社ではなく「自分たちが働き方を選ぶんだ」という気持ちですよね。会社より個人が強い時代なんだなと思いました。
小島:2020年のウェルネス経営推進プロジェクトメンバーは、コロナ禍で文化祭ができなくなってしまった当社の本社近くに位置する高校のオンライン文化祭を企画しました。立案の根本にあるのは社内・社外に限らず、ほかの人に喜んでもらうことが自分のしあわせという発想なのです。つまり、彼らが渇望しているのは、高級な車がほしいとかではなくて、多くの人に喜んでほしいということなんですね。しかし、社外の講演などで丸井グループのウェルネス経営、Well-being経営の話をすると、「それが企業の利益にどうつながるのですか」といまだに聞かれます。
石川:採用コストやブランディングコストが下がるので、コスト削減という意味でも大きなインパクトがあると思いますね。それに、しあわせ度が下がると、数年後に政治的、社会的な大混乱が起こるといわれています。旧ソ連の崩壊がそうだし、最近ではブレグジットもそう。したがってWell-beingは、社会的混乱の先行指標といわれています。混乱が起きてしあわせ度が下がるのではありません。しあわせ度が下がった結果、混乱が起こるのです。会社でもそうだと思います。部署単位で見た時に、たとえ業績が良くても、Well-beingやしあわせ度が下がり続けている部署では、その後に業績悪化が起こるかもしれません。だから、中長期的に安定して経営していくためにはWell-beingを下げないことが極めて重要だと考えられます。
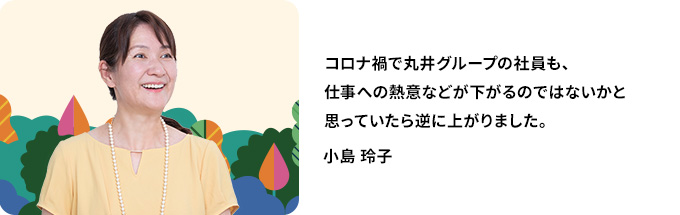
コロナ禍が変えた時間とお金の使い方への意識
石川:人々が何に時間を使っているのか、何にお金を使っているのかという両面を見ることがWell-beingではすごく大事です。お金の使い方も、数十年単位で見ると大きく変わってきていると思います。
青井:確かに時間とお金の使い方は変わってきていますね。それもたぶん時間のほうが変化は大きくて、その中に新しいお金の使い方みたいなものも入ってきていると感じます。
石川:自分が使う時間に合わせて、お金を配分すればいいと言っている人がいます。
青井:在宅時間が長くなれば、家のほうにお金を注ぎ込むようになりますよね。
石川:そうそう。例えば、起きている時間の10分の1を移動に使うのなら、10分の1のお金を移動に使っていいよねと。なるほどと思いました。いい時間を過ごしているか、いいお金の使い方をしているかは、その人の主観的なものでしかないのですが、それがたぶん今の時代のしあわせなのだと思います。
小島:より「良くある」(Well-being)ということですね。
石川:今回のコロナによってけっこう価値観が変わった気がします。限られた環境の中でどう時間とお金を使うのか。例えば、イギリスでは毎週、Well-beingの調査が行われているのですが、最近の調査結果が興味深いです。毎週ランダムに選ばれた2,000人に幸福度や満足度を聞いているのです。ここ10年間ずっと下がり続けているのですが、ロックダウンが始まったら、幸福度も満足度もぐっと上がったのです。もちろん苦しんだ方たちもたくさんいらっしゃると思いますが、国民全体として見ると幸福度も満足度も上がっている。その理由はわかっていないのですが、おそらく、これまでは資本主義の中でもっとお金があれば、もっと自由な時間を手に入れられるに違いないと思い込んできました。でも、与えられた限定的な空間の中で、何とかするしかないという状況になった時に、自分にとって大切なものは何かということを見直したのだと思います。
小島:丸井グループの社員も、仕事への熱意などが下がるのではないかと思っていたら逆に上がりました。ほぼ全員が受験するストレスチェックでワークエンゲージメント指数、ストレス指数ともに昨年より向上したのです。
石川:これは推測ですが、今この瞬間というものに、より集中できるようになったのだと思います。今までは思考が未来に飛んで、「もっともっと」となっていた、「More is Better」だったのが「Less is More」に変わってきたのかなと。
青井:そういうことの抽象度を上げていくと、「調和」みたいなことになるでしょうか。「もっともっと」の中に調和はないですからね。
石川:「しあわせ」というとすごく抽象的に思えますが、要は日常的にくり返す所作をいかに「いい感じ」にできるかということだと思っています。例えば洗い物。洗い物は手も荒れるし、つまらないと私は思っていたのですが、それではいかんと思ってキッチンにポータブルスピーカーを持ってきたのです。音楽を聴きながら洗い物をして初めて、なぜ当たり前に聞いていた音楽をキッチンには置いていなかったのだろうと、不思議に思いました。
小島:「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば人生が変わる。」という言葉があります。この変わり目が、今の時代なのかもしれませんね。
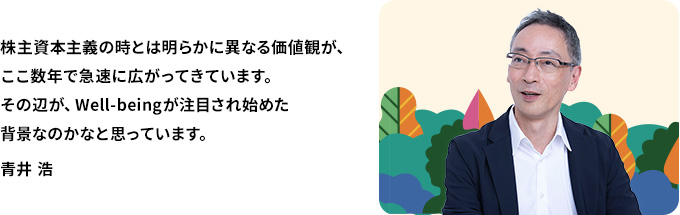
- 石川 善樹氏
医学博士/公益財団法人Well-being for Planet Earth 代表理事
株式会社丸井グループ アドバイザー1981年、広島県生まれ。予防医学研究社、博士(医学)。東京大学医学部健康科学・看護学科卒業。ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士号取得。公益財団法人Well-being for Planet Earth 代表理事。「人が良く生きるとは何か」をテーマとして、企業や大学とさまざまなプロジェクトを行う。専門は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念工学など。著書に『フルライフ』(NewsPicksパブリッシング)など。
- 青井 浩
株式会社丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員 CEO1986年当社入社、2005年4月より代表取締役社長に就任。創業以来の小売・金融一体の独自のビジネスモデルをベースに、ターゲット戦略の見直しや、ハウスカードから汎用カードへの転換、SC・定借化の推進など、さまざまな革新を進める。ステークホルダーとの共創を通じ、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現をめざす。2019年3月より男女共同参画会議 議員、2020年10月より世界経済フォーラム Global Future Council On Japan メンバー。
- 小島 玲子
株式会社丸井グループ 執行役員 ウェルネス推進部長 兼 専属産業医医師、医学博士。大手メーカーの専属産業医を約10年間務める傍ら、総合病院の心療内科にて定期外来診療を担当。2006年より北里大学大学院の産業精神保健学教室に在籍し、2010年、医学博士号を取得。翌年に丸井グループ専属産業医となり、2014年、健康推進部の新設にともなって部長に就任。2019年、執行役員に就任。著書に『産業保健活動事典』(共著、バイオコミュニケーションズ)、『改訂 職場面接ストラテジー』(共著、バイオコミュニケーションズ)など。




















